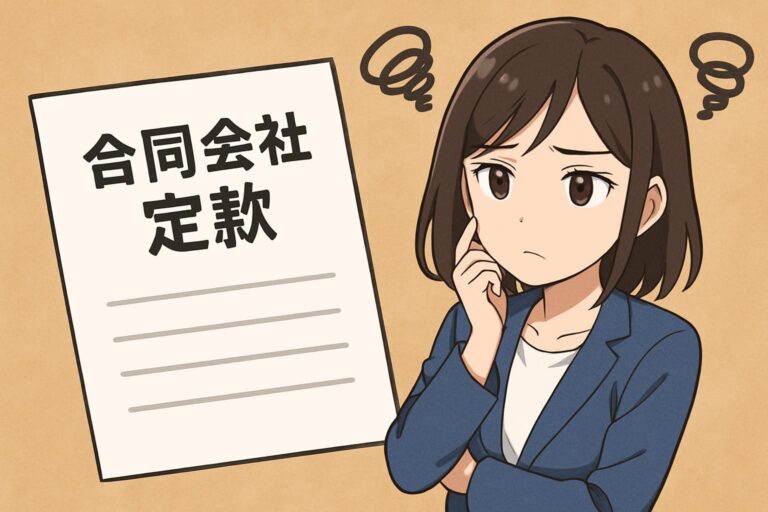合同会社を設立する際、定款の作成は避けて通れない重要な手続きです。
しかし、株式会社とは異なり公証人の認証が不要であることや、具体的にどのような事項を記載すべきかわからず、戸惑う方も多いのではないでしょうか。
この記事では、合同会社の定款作成に必要な知識を網羅的に解説します。
絶対的記載事項である商号・事業目的・本店所在地・社員・出資の正しい書き方から、相対的記載事項や任意的記載事項の選び方まで、具体的な記載例とともにご紹介します。
また、電子定款を利用することで印紙代4万円を節約できる方法や、書面定款との違い、必要な機器やソフトウェアについても詳しく説明します。
さらに、認証不要という合同会社特有のメリットを活かしながら、法務局への登記申請までスムーズに進めるための手順を順を追って解説していきます。
定款作成後の変更手続きや費用、業務執行社員・代表社員の設定、利益配分ルールなど、設立後に問題とならないための注意点も押さえています。
この記事を読むことで、専門家に依頼する場合でも自分で作成する場合でも、適切な判断ができる知識が身につきます。
合同会社の定款の基礎知識
定款とは何か
定款とは、会社の基本的なルールを定めた書面のことで、会社の憲法とも呼ばれる重要な文書です。
会社を設立する際には必ず作成しなければならず、会社の目的、組織、運営方法などの根本規則を記載します。
定款には、会社名(商号)、事業内容(目的)、本店の所在地、社員の氏名や出資額など、会社の骨格となる事項が記載されます。
一度作成した定款は会社の活動の指針となり、重要な意思決定を行う際の基準となります。
会社法では、定款に記載する事項を「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」の3つに分類しています。
絶対的記載事項は必ず記載しなければならない項目で、これらが欠けている定款は無効となります。
相対的記載事項は記載しなくても定款自体は有効ですが、記載しなければその事項の効力が生じないものです。
任意的記載事項は法令に違反しない範囲で自由に定められる事項です。
合同会社における定款の重要性
合同会社の定款は、株式会社以上に柔軟な会社運営を可能にする重要な役割を果たします。
合同会社は出資者である社員全員が経営に参加する会社形態であり、定款で社員間のルールを明確に定めておくことが、円滑な会社運営の鍵となります。
特に合同会社では、利益の配分方法を出資比率とは異なる割合で設定できるなど、定款の定めによって自由度の高い運営が可能です。
例えば、出資額は少なくても経営に大きく貢献する社員に対して、より多くの利益を配分するといった柔軟な設計ができます。
このような特徴を活かすためには、設立時に適切な定款を作成することが不可欠です。
また、合同会社では社員間の意見対立が生じた場合に備えて、意思決定の方法や社員の加入・退社に関するルールを定款で明確にしておくことが重要です。
定款で明確に定めておかないと、後々トラブルの原因となる可能性があります。
合同会社の定款は、会社の設立後も事業の拡大や環境の変化に応じて変更することができますが、変更には社員の同意が必要となるため、将来を見据えた慎重な作成が求められます。
株式会社の定款との主な違い
合同会社の定款と株式会社の定款には、作成手続きや記載内容において重要な違いがいくつか存在します。
これらの違いを理解することで、合同会社設立のメリットをより明確に把握できます。
| 項目 | 合同会社 | 株式会社 |
|---|---|---|
| 公証人の認証 | 不要 | 必要 |
| 認証手数料 | 0円 | 3万円~5万円 |
| 定款印紙代(書面の場合) | 4万円 | 4万円 |
| 出資者の呼称 | 社員 | 株主 |
| 機関設計 | シンプル(社員総会なし) | 複雑(株主総会、取締役など) |
| 利益配分 | 定款で自由に設定可能 | 出資比率に応じる |
最も大きな違いは公証人による認証が不要という点です。
株式会社を設立する場合は、作成した定款を公証役場に持参し、公証人の認証を受ける必要があります。
これには手数料として3万円から5万円程度かかりますが、合同会社ではこの手続きが不要なため、設立費用を抑えることができます。
記載内容においても違いがあります。
株式会社の定款では「株式」「株主」「株主総会」といった用語を使用しますが、合同会社では「持分」「社員」という用語を使用します。
また、株式会社では取締役や監査役などの機関設計について定款に記載する必要がありますが、合同会社では業務執行社員や代表社員について記載するだけでシンプルな構成となります。
利益配分に関しても大きな違いがあります。株式会社では原則として出資比率に応じた配当となりますが、合同会社では定款で自由に利益配分の割合を定めることができます。
この柔軟性は合同会社の大きな特徴であり、定款作成時に戦略的に活用することができます。
さらに、合同会社には株主総会に相当する機関がなく、重要事項の決定は社員の同意によって行われます。
この点も定款に反映され、意思決定のプロセスが株式会社よりもシンプルになっています。
合同会社の定款記載事項の詳細

合同会社の定款には、記載しなければならない事項と任意で記載できる事項があります。
これらを正しく理解し、適切に記載することが、会社設立後のトラブルを防ぐ上で非常に重要です。
必ず記載しなければならない絶対的記載事項
絶対的記載事項とは、会社法で定款に必ず記載しなければならないと定められている事項です。
これらの事項が一つでも欠けている場合、定款全体が無効となり、会社設立ができません。
合同会社の場合、以下の事項が絶対的記載事項として定められています。
| 記載事項 | 内容 | 法的根拠 |
|---|---|---|
| 商号 | 会社の名称 | 会社法第576条第1項第1号 |
| 目的 | 会社が行う事業内容 | 会社法第576条第1項第2号 |
| 本店所在地 | 会社の本店の所在地 | 会社法第576条第1項第3号 |
| 社員の氏名又は名称及び住所 | 出資者である社員の情報 | 会社法第576条第1項第4号 |
| 社員の全部を有限責任社員とする旨 | 合同会社の社員は全員有限責任であることの明記 | 会社法第576条第1項第5号 |
| 社員の出資の目的及びその価額 | 各社員が何を出資し、その評価額はいくらか | 会社法第576条第1項第6号 |
商号の決め方と注意点
商号とは会社の正式な名称のことで、定款の最も重要な記載事項の一つです。
合同会社の商号には必ず「合同会社」という文字を入れなければなりません。
これは会社法第6条第2項で定められており、違反すると登記が受理されません。
商号は「合同会社○○」のように前に付ける形でも、「○○合同会社」のように後ろに付ける形でも構いません。
また、アルファベットや数字を使用することも可能ですが、使用できる記号は限られています。
具体的には、「&」「’」「,」「-」「.」「・」の6種類の記号のみが使用可能です。
商号を決定する際には、同一住所に同一商号が既に登記されていないか確認する必要があります。
同一住所で同一商号は登記できないため、事前に法務局で商号調査を行うことをお勧めします。
また、他社の著名な商号を使用すると不正競争防止法に抵触する可能性があるため、慎重に検討しましょう。
定款への記載例としては、「当会社は、合同会社○○と称する。」または「第1条(商号) 当会社は、合同会社○○と称する。」のように記載します。
事業目的の適切な記載方法
事業目的は、会社が行う事業の内容を記載する項目です。
目的として記載されていない事業を行うことは原則としてできないため、将来行う可能性のある事業も含めて記載することが重要です。
事業目的を記載する際には、以下の4つの要件を満たす必要があります。
| 要件 | 説明 |
|---|---|
| 適法性 | 法律に違反する事業は記載できない |
| 営利性 | 営利を目的とする事業である必要がある |
| 明確性 | 第三者が見て何の事業か理解できる程度に具体的である必要がある |
| 具体性 | 抽象的すぎる表現は避け、具体的に記載する必要がある |
事業目的は複数記載することができ、一般的には3項目から10項目程度を記載するケースが多く見られます。
記載する順序は自由ですが、主たる事業から順に記載するのが通例です。
また、将来的に事業を拡大する可能性を考慮して、「前各号に付帯関連する一切の業務」という包括的な条項を最後に入れることが一般的です。
この記載により、主たる事業に付随する業務を柔軟に行うことができます。
具体的な記載例としては、「1. ○○の製造及び販売」「2. ○○に関するコンサルティング業務」「3. 前各号に付帯関連する一切の業務」のように、箇条書きで明確に記載します。
本店所在地の書き方
本店所在地は、会社の本拠地となる住所を記載する項目です。
定款における本店所在地の記載方法には、最小行政区画まで記載する方法と、詳細な住所まで記載する方法の2種類があります。
最小行政区画まで記載する方法とは、市区町村までを記載し、番地以下は記載しない方法です。
例えば「当会社は、本店を東京都渋谷区に置く。」のように記載します。
この方法の利点は、同一市区町村内で移転する場合でも定款変更が不要で、登記変更のみで済むという点です。
一方、詳細な住所まで記載する方法は、「当会社は、本店を東京都渋谷区○○1丁目2番3号に置く。」のように、番地まで具体的に記載する方法です。
この方法は所在地が明確になりますが、同一市区町村内での移転であっても定款変更の手続きが必要になります。
一般的には、将来的な移転の可能性を考慮して、最小行政区画までの記載にとどめるケースが多く見られます。
ただし、登記申請の際には具体的な番地まで記載した住所が必要となるため、別途決定する必要があります。
社員に関する事項
合同会社における「社員」とは、出資者のことを指します。
株式会社における株主に相当する立場です。定款には、社員の氏名または名称および住所を必ず記載しなければなりません。
社員には個人だけでなく法人もなることができます。
個人の場合は氏名と住所を、法人の場合は法人名と本店所在地を記載します。
複数の社員がいる場合は、全員の情報を漏れなく記載する必要があります。
また、合同会社の特徴として、社員全員が有限責任社員である旨を明記する必要があります。
これは「当会社の社員は、全て有限責任社員とする。」のように記載します。この記載により、社員は出資額を限度としてのみ会社の債務について責任を負うことが明確になります。
社員が複数いる場合、業務執行社員や代表社員を定めることができますが、これらの記載は絶対的記載事項ではなく、相対的記載事項または任意的記載事項に該当します。
出資に関する事項
出資に関する事項として、各社員の出資の目的およびその価額を定款に記載する必要があります。
出資の目的とは、金銭出資か現物出資かの別と、現物出資の場合はその内容を指します。
金銭出資の場合は、「社員○○は、金100万円を出資する。」のように記載します。
現物出資の場合は、「社員○○は、別紙財産目録記載の不動産を出資し、その価額は500万円とする。」のように、出資する財産の内容と評価額を明記します。
出資額の総額は会社の資本金となります。合同会社には最低資本金の規制がないため、1円からでも設立可能ですが、実務上は事業を開始するために必要な資金を考慮して出資額を決定します。
また、社員が複数いる場合、出資比率によって利益配分や議決権の割合が原則として決まります。
ただし、合同会社では定款で別段の定めをすることにより、出資比率とは異なる利益配分や議決権の割合を設定することも可能です。
| 出資の種類 | 内容 | 記載例 |
|---|---|---|
| 金銭出資 | 現金で出資する | 社員○○は、金300万円を出資する。 |
| 現物出資 | 金銭以外の財産で出資する(不動産、動産、知的財産権など) | 社員○○は、別紙財産目録記載の○○を出資し、その価額は200万円とする。 |
記載することで効力が生じる相対的記載事項
相対的記載事項とは、定款に記載しなくても定款自体は有効ですが、記載しなければその事項の効力が生じない事項を指します。
会社の運営において重要な取り決めを定款に明記することで、法的な効力を持たせることができます。
合同会社における主な相対的記載事項には以下のようなものがあります。
| 相対的記載事項 | 内容 | 法的根拠 |
|---|---|---|
| 業務執行社員の定め | 業務を執行する社員を定める | 会社法第590条 |
| 代表社員の定め | 会社を代表する社員を定める | 会社法第599条 |
| 損益分配の割合 | 出資比率と異なる利益配分を定める | 会社法第622条 |
| 存続期間または解散事由 | 会社の存続期間や解散となる条件を定める | 会社法第641条 |
業務執行社員を定める場合、「当会社の業務執行社員は、社員○○とする。」のように記載します。
定款で業務執行社員を定めない場合は、社員全員が業務執行権限を持つことになります。
代表社員についても同様で、「当会社の代表社員は、業務執行社員○○とする。」のように定款に記載することで、対外的に会社を代表する権限を特定の社員に与えることができます。
代表社員を定めない場合は、業務執行社員全員が会社を代表することになります。
損益分配の割合については、会社法の原則では出資比率に応じて配分されますが、定款に「利益または損失の配分は、各社員の出資の価額にかかわらず、社員の協議により決定する。」のように記載することで、出資比率とは異なる配分方法を採用することができます。
これは合同会社の大きな特徴の一つです。
自由に定められる任意的記載事項
任意的記載事項とは、法律の規定に反しない限り、会社が自由に定款に記載できる事項です。
記載しなくても定款は有効であり、記載しなくても法律上の効力には影響しませんが、会社運営のルールを明確にするために記載されることが多い事項です。
任意的記載事項の主な例としては、以下のようなものがあります。
| 任意的記載事項 | 記載する目的 |
|---|---|
| 事業年度 | 決算期を明確にするため |
| 社員総会に関する事項 | 社員総会の招集方法や議決方法を定めるため |
| 公告の方法 | 会社の公告をどのように行うかを定めるため |
| 競業避止義務 | 社員が同種の事業を行うことを制限するため |
| 社員の加入 | 新たな社員を加入させる際の手続きを定めるため |
| 社員の退社 | 社員が退社する際の条件や手続きを定めるため |
事業年度は、「当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。」のように記載します。
事業年度を定めることで、決算のタイミングが明確になり、税務申告や会計処理がスムーズに行えます。
公告の方法については、「当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。」または「当会社の公告は、電子公告により行う。」のように記載します。
公告の方法を定款に記載しない場合、官報による公告が必要となりますが、電子公告を選択することでコストを削減できる場合があります。
競業避止義務については、「社員は、当会社の承諾を得ずに、自己または第三者のために当会社の事業の部類に属する取引をしてはならない。」のように記載することで、社員が会社と競合する事業を行うことを制限できます。
これにより、会社の利益を保護することができます。
社員の加入や退社に関する規定も重要な任意的記載事項です。
「新たに社員を加入させるには、社員総会の決議を要する。」や「社員が退社する場合は、事業年度終了の3ヶ月前までに会社に予告しなければならない。」のように記載することで、社員の入退社に関するルールを明確にできます。
任意的記載事項は、会社の実情や社員間の合意に基づいて柔軟に定めることができます。
ただし、一度定款に記載した事項を変更するには定款変更の手続きが必要となるため、将来的な事業展開も考慮して慎重に検討することが重要です。
合同会社の定款作成方法

合同会社の定款を作成する際には、適切な手順を踏むことで、スムーズに会社設立を進めることができます。
ここでは、定款作成の準備から具体的な作成手順、そして実際に使える記載例まで、実践的な内容を解説します。
定款作成の準備
定款作成を始める前に、いくつかの重要事項を決定しておく必要があります。
これらの事項は定款の絶対的記載事項となるため、事前に社員全員で十分に協議しておくことが重要です。
まず、会社の商号を決定します。商号には必ず「合同会社」という文字を入れる必要があり、前株(合同会社○○)または後株(○○合同会社)のいずれかの形式を選択します。
同一住所に同一商号の会社がないか、法務局で事前に調査しておくと安心です。
次に、事業目的を明確にします。
将来行う可能性のある事業も含めて、複数の目的を記載することが一般的です。金融機関から融資を受ける際や、許認可が必要な事業を行う際には、事業目的の記載が審査対象となるため、慎重に検討する必要があります。
本店所在地については、最小行政区画まで定款に記載する方法と、詳細な住所まで記載する方法があります。
将来の移転の可能性を考慮して決定すると良いでしょう。
社員の構成と出資額も事前に確定させます。
誰が社員となり、各社員がいくら出資するのか、また業務執行社員や代表社員を誰にするのかを明確にしておきます。
| 準備事項 | 検討内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 商号 | 会社名の決定、前株・後株の選択 | 「合同会社」の文字が必須、同一商号の確認 |
| 事業目的 | 現在および将来の事業内容 | 適法性、明確性、具体性が必要 |
| 本店所在地 | 会社の住所 | 記載レベル(最小行政区画or詳細住所)の選択 |
| 社員・出資 | 社員の氏名、出資額、出資割合 | 業務執行社員、代表社員の決定 |
| 事業年度 | 決算月の決定 | 税務上の都合も考慮 |
書面定款の作成手順
書面定款は、紙の文書として定款を作成する方法です。
作成手順は比較的シンプルですが、いくつかの形式的な要件を満たす必要があります。
まず、A4サイズの用紙を使用し、縦書きまたは横書きで定款の本文を作成します。
ワードプロセッサソフトを使って作成することが一般的です。
文字サイズや余白に法的な規定はありませんが、読みやすさを考慮して作成します。
定款の本文は、「第○条」という形式で条文を記載していきます。
絶対的記載事項である商号、事業目的、本店所在地、社員の氏名・住所、社員の出資目的・価額・履行時期を必ず記載します。
これらが一つでも欠けていると、定款自体が無効となってしまいます。
定款の末尾には、作成年月日を記載し、「以上、合同会社○○設立のため、社員全員の合意により本定款を作成する」などの文言を入れます。
その後、社員全員が署名または記名押印を行います。
書面定款を作成する場合、収入印紙4万円分を定款に貼付する必要があります。
印紙は郵便局や法務局で購入できます。印紙を貼付した後、消印を行いますが、定款に押印した印鑑と同じ印鑑で消印することが一般的です。
定款は製本テープなどで製本し、製本の継ぎ目に社員全員の実印で契印を押します。
契印は、ページの差し替えを防止するための重要な手続きです。
書面定款は、会社保管用と法務局提出用の最低2部を作成します。
社員が複数いる場合は、各社員が1部ずつ保管できるよう、必要部数を作成しておくと良いでしょう。
電子定款の作成手順
電子定款は、PDFファイル形式で作成した定款に電子署名を付与したものです。
書面定款に必要な4万円の収入印紙が不要になるため、コスト削減につながります。
電子定款の作成には、通常の定款作成作業に加えて、電子署名を行うための特別な準備が必要となります。
初期投資や手続きの複雑さから、専門家に依頼するケースも多くありますが、自分で作成することも可能です。
必要な機器とソフトウェア
電子定款を自分で作成する場合、以下の機器とソフトウェアを準備する必要があります。
まず、マイナンバーカードとICカードリーダライタが必須となります。マイナンバーカードは、社員のうち一人が電子署名を行うために使用します。
ICカードリーダライタは、マイナンバーカードの情報を読み取るための機器で、家電量販店やオンラインショップで数千円程度で購入できます。
次に、PDF編集ソフトウェアが必要です。
Adobe Acrobat Reader DCは無料ですが、電子署名を付与するにはAdobe Acrobatなどの有料版が必要になる場合があります。
ただし、後述する法務省の登記・供託オンライン申請システムを利用する場合は、専用のソフトウェアが提供されています。
また、電子証明書を取得する必要があります。
個人の場合、マイナンバーカードに格納されている電子証明書を使用できます。
この電子証明書を利用するために、公的個人認証サービスのクライアントソフトをインストールします。
| 必要なもの | 内容 | 費用目安 |
|---|---|---|
| マイナンバーカード | 電子署名に使用 | 無料(発行手数料なし) |
| ICカードリーダライタ | マイナンバーカード読み取り用 | 2,000円~5,000円程度 |
| PDF作成ソフト | 定款をPDF化 | 無料~数万円 |
| 電子署名ソフト | PDFに電子署名を付与 | 無料(公的個人認証サービス利用の場合) |
これらの初期投資は合計で数千円から1万円程度となりますが、印紙代4万円が不要になることを考えると、十分にメリットがあります。
定款作成時に使える記載例とサンプル
実際の定款作成において参考となる記載例を示します。以下は、一般的な合同会社の定款のサンプルです。条文の構成や表現方法を参考にしてください。
定款の冒頭部分は、以下のような形式で始めます。
【記載例:定款の冒頭部分】
| 「合同会社○○定款」というタイトルを中央に記載し、続けて以下のように記載します。 「第1条(商号)当会社は、合同会社○○と称する。」 「第2条(目的)当会社は、次の事業を営むことを目的とする。 1. ○○の企画、開発、製造、販売及びコンサルティング業務 2. △△に関する情報提供サービス業 3. 前各号に附帯関連する一切の事業」 「第3条(本店の所在地)当会社は、本店を東京都○○区に置く。」 |
出資に関する記載例は以下の通りです。
| 「第4条(社員の氏名及び住所)当会社の社員の氏名及び住所は、次のとおりである。 住所 東京都○○区○○1丁目2番3号 氏名 山田太郎 住所 東京都○○区○○4丁目5番6号 氏名 佐藤花子」 「第5条(社員の出資)社員の出資の価額は、次のとおりとする。 山田太郎 金200万円 佐藤花子 金100万円 合計 金300万円」 |
業務執行や代表に関する記載例は以下のようになります。
| 「第6条(業務執行社員)当会社の業務執行社員は、次のとおりとする。 山田太郎 佐藤花子」 「第7条(代表社員)当会社の代表社員は、次のとおりとする。 山田太郎」 「第8条(事業年度)当会社の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。」 相対的記載事項として、利益配分について特別な定めをする場合の記載例は以下の通りです。 「第9条(利益の配当)当会社の利益の配当は、出資割合にかかわらず、次の割合による。 山田太郎 60% 佐藤花子 40%」 |
任意的記載事項の例として、社員の競業避止義務を緩和する場合は以下のように記載します。
| 「第10条(競業の許可)社員は、会社の承認を得て、自己又は第三者のために会社の事業の部類に属する取引をすることができる。」 |
定款の末尾は、以下のような形式でまとめます。
| 「以上、合同会社○○設立のため、社員全員の同意により本定款を作成し、各社員が次に記名押印する。 令和○年○月○日 社員 住所 東京都○○区○○1丁目2番3号 氏名 山田太郎 印 社員 住所 東京都○○区○○4丁目5番6号 氏名 佐藤花子 印」 |
定款の記載内容は会社の実態に合わせて調整する必要があり、これらの記載例はあくまで参考としてください。
特に事業目的や出資額、利益配分などは、各社の状況に応じて適切に記載することが重要です。
また、将来的な事業展開や社員の追加などを見越して、柔軟性のある条文にしておくことも検討すべきです。
例えば、本店所在地を最小行政区画(市区町村)までの記載にとどめることで、同じ区内での移転であれば定款変更が不要になります。
合同会社の定款は公証人の認証が不要

合同会社の設立において大きなメリットとなるのが、定款の公証人による認証が不要という点です。
株式会社の設立では必須となる公証人認証の手続きが省略できることで、設立にかかる費用と時間を大幅に削減することができます。
認証不要の理由と法的根拠
合同会社の定款が公証人の認証を必要としない理由は、会社法の規定に基づいています。
会社法第30条第1項では、株式会社の設立における定款作成について公証人の認証を受けなければならないと明記されていますが、持分会社である合同会社については同様の規定が設けられていません。
この違いは、株式会社と合同会社の組織構造の違いに起因します。
株式会社は所有と経営が分離しており、多数の株主が存在する可能性があるため、定款の真正性を公的に担保する必要性が高いと考えられています。
一方、合同会社は出資者である社員自らが経営に参加する構造であり、社員全員の合意により定款が作成されるため、公証人による認証という手続きを経なくても定款の真正性が確保されると判断されています。
また、持分会社は閉鎖的な組織形態であることから、定款の内容について第三者との関係で問題が生じる可能性が相対的に低いという点も、認証不要とされている背景にあります。
認証不要による設立コストの削減
公証人認証が不要であることにより、合同会社の設立では大幅なコスト削減が実現できます。
具体的な費用の違いを以下の表で示します。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 定款の認証手数料 | 30,000円~50,000円 | 0円 |
| 定款の謄本手数料 | 約2,000円 | 0円 |
| 収入印紙代(書面定款の場合) | 40,000円 | 40,000円 |
| 登録免許税 | 150,000円(最低額) | 60,000円(最低額) |
| 合計(書面定款の場合) | 約222,000円~ | 100,000円 |
この表からわかるように、公証人認証が不要なだけで3万円から5万円程度のコスト削減が可能です。
さらに登録免許税の差額も含めると、合同会社の設立費用は株式会社と比べて10万円以上安くなります。
電子定款を作成すれば収入印紙代の4万円も不要となるため、合同会社の設立費用は最低6万円まで抑えることが可能です。
これは起業時の資金が限られている場合や、スモールビジネスを始める際に大きなメリットとなります。
認証不要による手続きの簡素化
公証人認証が不要であることは、金銭面だけでなく手続き面でも大きなメリットをもたらします。
株式会社の設立では以下のような手間が必要となりますが、合同会社ではこれらがすべて不要です。
まず、株式会社の定款作成では、公証役場への事前連絡と定款案の確認が必要です。
定款の内容に不備があれば修正を求められ、何度もやり取りを繰り返すことになる場合があります。
公証役場の営業時間は平日の日中に限られているため、仕事をしながら設立手続きを進める場合には時間的な制約が大きくなります。
次に、認証当日は発起人全員または代理人が公証役場に出向く必要があります。
認証には予約が必要で、繁忙期には数週間待たされることもあります。
認証手続き自体も30分から1時間程度かかり、その間は公証役場で待機しなければなりません。
合同会社の場合、これらの手続きがすべて不要となるため、定款を作成したらすぐに次の設立手続きに進むことができます。
設立までのスケジュールを大幅に短縮でき、ビジネスチャンスを逃さずに事業を開始できるという点で、時間的価値も非常に大きいといえます。
認証不要でも記載内容の正確性は必須
公証人の認証が不要であるからといって、定款の記載内容を軽視してはいけません。
むしろ、公証人によるチェックが入らないからこそ、自ら正確性を担保する責任が重くなると考えるべきです。
定款に法的な不備があった場合、株式会社であれば公証人認証の段階で指摘されて修正する機会がありますが、合同会社ではそのチェック機能がありません。
そのため、誤った内容や法令に違反する内容が記載されたまま設立登記を申請してしまうリスクがあります。
法務局での設立登記申請の段階で定款の内容に不備が発見されると、登記申請が却下または補正を求められることになります。
この場合、定款を修正して再度申請しなければならず、結果的に時間とコストがかかってしまいます。
特に絶対的記載事項に不備があると、設立自体が無効となる可能性もあります。
また、設立後に定款の不備が発覚した場合には、定款変更の手続きが必要となり、変更内容によっては登記申請と登録免許税の支払いが必要になります。
事業開始後にこのような手続きを行うことは、時間的にも金銭的にも大きな負担となります。
したがって、合同会社の定款を作成する際には、以下の点に特に注意を払う必要があります。
第一に、絶対的記載事項である商号、事業目的、本店所在地、社員の氏名または名称および住所、社員の出資の目的およびその価額または評価の基準については、会社法の規定に従って正確に記載しなければなりません。
特に事業目的については、具体性と適法性を満たす必要があり、将来行う可能性のある事業も含めて適切に記載することが重要です。
第二に、相対的記載事項として定款に記載しようとする事項については、その効力要件や法的な制約を十分に理解した上で記載する必要があります。
例えば、利益配分を出資割合と異なる方法で行う場合、業務執行社員を限定する場合、会社の存続期間を定める場合などは、記載方法を誤ると意図した効力が生じない可能性があります。
第三に、任意的記載事項についても、法令や公序良俗に反する内容を記載することはできません。
また、記載した内容は社員を拘束する効力を持つため、将来の事業運営に支障をきたさないよう慎重に検討する必要があります。
これらの点を確実にするためには、専門家である司法書士や行政書士に定款の内容をチェックしてもらうことも有効な方法です。
認証が不要であっても、専門家による助言を受けることで、法的リスクを最小限に抑えた適切な定款を作成することができます。
定款作成から会社設立までの流れ

合同会社の設立は、定款の作成から始まり、法務局での登記完了まで、いくつかの重要な手続きを経る必要があります。
ここでは、設立までの各ステップを順を追って詳しく解説します。
定款作成
合同会社の設立において、最初に行うべき作業が定款の作成です。
定款は会社の根本規則を定めるもので、合同会社の場合は公証人による認証が不要という大きな特徴があります。
定款作成の具体的な手順は以下の通りです。
まず、社員全員で定款の内容について協議し、絶対的記載事項である商号、事業目的、本店所在地、社員の氏名または名称および住所、社員全員が有限責任社員である旨、社員の出資の目的およびその価額を明確に決定します。
次に、相対的記載事項や任意的記載事項についても、会社の実情に合わせて検討します。
業務執行社員や代表社員の定め、利益配分の割合、事業年度などは、後々のトラブルを避けるために明確に定めておくことが重要です。
定款は書面または電子データで作成します。
書面の場合は、製本した定款に社員全員が署名または記名押印します。
電子定款の場合は、電子署名を行います。
電子定款を選択すると印紙代4万円が不要になるため、コスト面でのメリットがあります。
| 定款の種類 | 作成方法 | 印紙代 | 認証費用 |
|---|---|---|---|
| 書面定款 | 紙に印刷して製本 | 40,000円 | 不要 |
| 電子定款 | PDF形式で作成 | 不要 | 不要 |
定款の作成が完了したら、原本を最低でも2通作成します。
1通は法務局への登記申請時に提出し、もう1通は会社保管用として大切に保管します。
出資金の払込
定款の作成が完了したら、次は社員による出資金の払込を行います。
合同会社では、定款作成後、設立登記の申請までに出資金の払込を完了させる必要があります。
出資金の払込方法には、金銭出資と現物出資の2種類があります。
金銭出資の場合は、発起人である社員の個人名義の銀行口座に各社員が出資金を振り込む形で行います。
この時点ではまだ会社が成立していないため、会社名義の口座は開設できません。
払込を行う際の注意点として、以下の事項を押さえておく必要があります。
まず、払込金額は定款に記載した各社員の出資金額と一致していなければなりません。
また、振込記録が残るように、必ず銀行振込またはATM振込で行います。
現金を直接口座に入金する方法は、払込の証明が困難になるため避けるべきです。
複数の社員がいる場合は、各社員が個別に振り込むことで、誰がいくら出資したかが通帳の記録から明確になります。
代表社員が自分の口座に払い込む場合でも、一度出金してから改めて振り込む形をとることで、払込の事実を明確に記録できます。
払込が完了したら、以下の書類を準備します。
- 払込があったことを証する書面(代表社員が作成)
- 通帳のコピー(表紙、裏表紙、払込記録のページ)
払込があったことを証する書面には、払込金額の総額、払込があった株数、1株の払込金額、払込の日付などを記載し、代表社員が署名または記名押印します。
登記申請書類の準備
出資金の払込が完了したら、法務局に提出する設立登記申請書類を準備します。
合同会社の設立登記に必要な書類は多岐にわたるため、漏れがないよう慎重に準備する必要があります。
設立登記申請に必要な主な書類は以下の通りです。
| 書類名 | 部数 | 備考 |
|---|---|---|
| 合同会社設立登記申請書 | 1通 | A4サイズで作成 |
| 定款 | 1通 | 原本を提出 |
| 代表社員、本店所在地及び資本金決定書 | 1通 | 定款で定めていない場合 |
| 代表社員の就任承諾書 | 1通 | 定款で定めていない場合 |
| 払込があったことを証する書面 | 1通 | 通帳のコピーを添付 |
| 印鑑届出書 | 1通 | 代表社員の実印を届出 |
| 印鑑証明書 | 各1通 | 代表社員全員分(発行後3か月以内) |
合同会社設立登記申請書には、商号、本店所在地、登記の事由、課税標準金額、登録免許税、添付書類などを正確に記載します。
登録免許税は、資本金額の0.7%(ただし6万円に満たない場合は6万円)を現金で納付するか、収入印紙で納めます。
代表社員、本店所在地及び資本金決定書は、定款でこれらの事項を具体的に定めていない場合に必要となります。
例えば、定款で本店所在地を「東京都渋谷区」としか記載していない場合、具体的な番地を決定したことを証する書面として提出します。
印鑑届出書は、会社の実印を法務局に登録するための書類です。
代表社員の個人実印で押印し、印鑑証明書を添付します。
この会社実印は、今後の重要な契約や登記手続きで使用することになるため、慎重に選定し管理する必要があります。
現物出資がある場合は、追加で以下の書類が必要になります。
- 財産引継書
- 資本金の額の計上に関する証明書
- 現物出資した財産の評価証明(500万円を超える場合)
すべての書類を揃えたら、申請書類一式を左側2か所でホチキス止めし、各ページの綴じ目に社員全員の契印(または代表社員の契印)を押します。
法務局への設立登記申請
必要書類がすべて揃ったら、本店所在地を管轄する法務局に設立登記の申請を行います。
登記申請を行った日が会社の設立日となるため、設立日にこだわりがある場合は、その日に申請する必要があります。
法務局への申請方法には、以下の3つの方法があります。
| 申請方法 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 窓口申請 | 法務局の窓口に直接持参 | 受付時間は平日8:30~17:15 |
| 郵送申請 | 書留郵便で送付 | 到達日が申請日となる |
| オンライン申請 | インターネット経由で申請 | 電子証明書が必要 |
窓口申請の場合は、法務局の登記相談窓口で事前に書類をチェックしてもらうことができます。
初めて会社設立を行う場合は、この事前チェックを利用することで、書類の不備による申請却下を防ぐことができます。
ただし、法務局は平日のみの営業で、昼休み時間や年末年始は窓口が閉まっているため、事前に営業日時を確認しておく必要があります。
郵送申請の場合は、書類一式を書留郵便または簡易書留で送付します。
普通郵便では送付できません。
郵送の場合、法務局に書類が到着した日が申請日となるため、特定の日を設立日にしたい場合は、配達日を考慮して余裕を持って発送する必要があります。
オンライン申請は、登記・供託オンライン申請システムを利用して行います。
この方法では、一部の書類をPDF形式で送信し、原本が必要な書類のみを後日郵送または持参します。
オンライン申請には電子証明書の取得が必要ですが、将来的に変更登記などをオンラインで行いたい場合は、最初から慣れておくメリットがあります。
申請時には、登録免許税を納付します。
現金で納付する場合は、法務局内の印紙売場で収入印紙を購入し、申請書に貼付します。
金融機関で納付する方法もあり、この場合は納付済証を申請書に添付します。
申請後、法務局から補正(修正)の連絡が来る場合があります。
これは書類に不備がある場合に行われるもので、指定された期限内に補正を行わないと申請が却下されてしまいます。
補正の連絡方法は、申請書に記載した連絡先に電話または書面で通知されます。
登記完了後の手続き
登記申請から通常1週間から10日程度で登記が完了します。
登記完了予定日は、申請時に法務局で確認できるほか、法務局のウェブサイトでも公開されています。
登記が完了したら、以下の書類を法務局で取得します。
これらの書類は、今後の各種手続きで必要となるため、複数部取得しておくことをお勧めします。
| 書類名 | 用途 | 手数料 |
|---|---|---|
| 登記事項証明書(履歴事項全部証明書) | 会社の存在証明、各種契約・届出 | 1通600円 |
| 印鑑証明書 | 重要契約、金融機関口座開設 | 1通450円 |
| 印鑑カード | 印鑑証明書の取得に必要 | 無料 |
登記事項証明書は、会社が正式に設立されたことを証明する公的書類です。
銀行口座の開設、税務署への届出、許認可の申請など、あらゆる場面で必要となります。
最低でも5通程度は取得しておくと、各種手続きをスムーズに進められます。
印鑑カードは、会社の印鑑証明書を取得する際に必要なカードです。
登記完了後、印鑑カード交付申請書を法務局に提出することで発行されます。
このカードがあれば、代表社員本人でなくても印鑑証明書を取得できるため、大切に保管する必要があります。
登記完了後、速やかに行うべき主な手続きは以下の通りです。
- 税務署への法人設立届出書の提出(設立から2か月以内)
- 都道府県税事務所への法人設立届出書の提出(設立から15日以内が目安)
- 市区町村役場への法人設立届出書の提出(設立から15日以内が目安)
- 年金事務所での社会保険の加入手続き(設立から5日以内)
- 労働基準監督署での労働保険の手続き(従業員を雇用する場合)
- ハローワークでの雇用保険の手続き(従業員を雇用する場合)
- 金融機関での法人口座開設
税務署への届出では、法人設立届出書のほか、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書なども同時に提出すると効率的です。
これらの届出により、税務上の優遇措置を受けることができます。
社会保険の加入は、代表社員1名だけの会社でも義務となります。
年金事務所で健康保険・厚生年金保険の加入手続きを行い、保険料の納付方法などを確認します。
法人口座の開設は、登記事項証明書、印鑑証明書、会社の印鑑、代表社員の本人確認書類などを持参して金融機関で手続きを行います。
最近は、法人口座開設の審査が厳しくなっているため、事業の実態を説明できる資料(事業計画書、パンフレット、ウェブサイトなど)も用意しておくとスムーズです。
これらの手続きをすべて完了させることで、合同会社としての事業活動を本格的に開始できる体制が整います。
各手続きには期限が設けられているものも多いため、登記完了後は速やかに計画的に進めることが重要です。
電子定款作成のメリットと方法
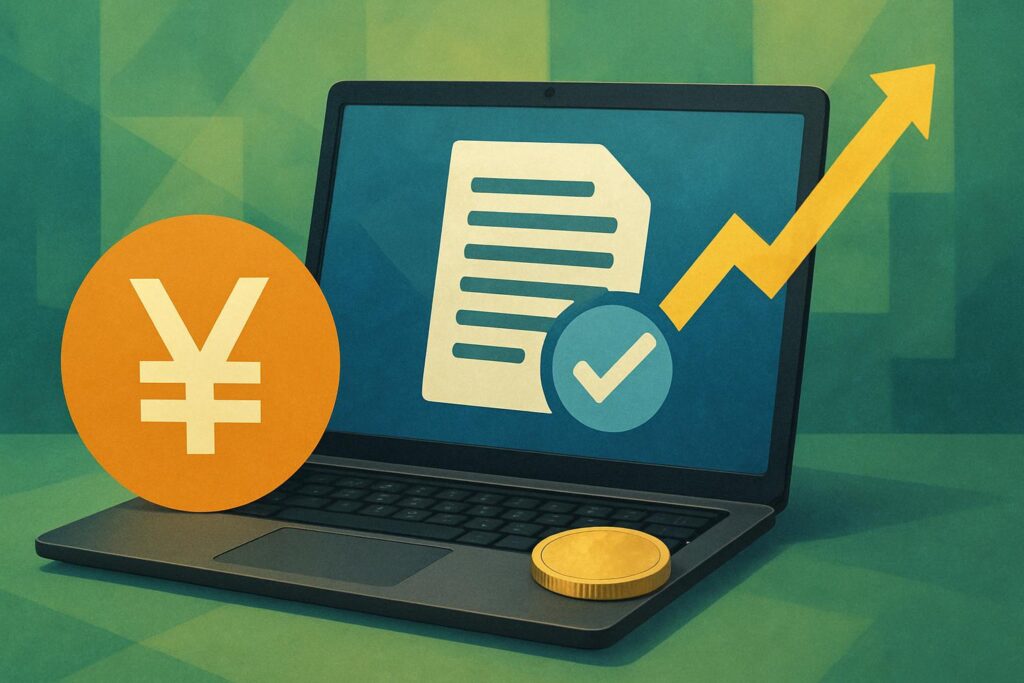
合同会社を設立する際、定款を電子形式で作成することで大きなコスト削減と効率化が実現できます。
ここでは電子定款の具体的なメリットと作成方法について、初めての方にもわかりやすく解説します。
印紙代4万円が節約できる
電子定款の最大のメリットは、収入印紙代4万円が不要になるという点です。
書面で定款を作成する場合、印紙税法により4万円分の収入印紙を貼付する必要がありますが、電子定款はこの対象外となります。
これは電子文書が印紙税法上の「課税文書」に該当しないためです。
合同会社の場合は株式会社と異なり公証人の認証が不要なため、電子定款を選択すれば純粋に4万円のコスト削減が可能となります。
ただし、電子定款を作成するためには専用の機器やソフトウェアが必要となるため、初期投資と4万円の節約額を比較検討することが重要です。
自分で環境を整える場合は、ICカードリーダーや電子証明書の取得費用などで1万円から2万円程度かかることを想定しておきましょう。
電子定款に必要な準備
電子定款を作成するには、以下の準備が必要です。
事前にしっかりと確認しておくことで、スムーズな作成が可能となります。
| 必要なもの | 詳細 | 費用目安 |
|---|---|---|
| マイナンバーカード | 電子署名に使用する電子証明書が格納されている | 無料(発行手数料のみ) |
| ICカードリーダー | マイナンバーカードを読み取るための機器 | 2,000円~5,000円程度 |
| PDF編集ソフト | Adobe Acrobat(有料版)など電子署名が可能なソフト | 月額1,500円程度または買い切り版 |
| パソコン | Windows推奨(Macでも可能だが設定が複雑) | 既存のものを使用可 |
マイナンバーカードに格納されている電子証明書には有効期限があります。
発行から5回目の誕生日までとなっているため、期限切れの場合は市区町村の窓口で更新手続きが必要です。
また、電子署名を行うためには署名用電子証明書のパスワードが必要となります。
マイナンバーカード受取時に設定した6桁から16桁の英数字のパスワードですので、忘れないよう管理しておきましょう。
自分で作成する方法
電子定款を自分で作成する場合の具体的な手順を解説します。
初めての方でも順を追って進めることで作成が可能です。
まず、定款の内容をワープロソフト(Microsoft WordやGoogleドキュメントなど)で作成します。
記載内容は書面定款と同じで、絶対的記載事項をすべて含める必要があります。
内容に誤りがないか十分に確認してから次のステップに進みましょう。
次に、作成した定款文書をPDF形式に変換します。
この際、編集可能な通常のPDFとして保存することが重要です。
画像PDFやスキャンしたPDFでは電子署名ができません。
PDF化した定款に電子署名を付与します。
Adobe Acrobatなどの対応ソフトウェアを使用し、以下の手順で進めます。
- ICカードリーダーにマイナンバーカードをセットする
- Adobe Acrobatで定款PDFファイルを開く
- 「証明書」メニューから「デジタルIDの管理」を選択
- マイナンバーカードの電子証明書を読み込む
- 定款PDFに電子署名を追加する
- 署名用パスワードを入力して署名を完了する
電子署名が完了した定款は、CD-RまたはDVD-Rなどの記録媒体に保存します。
USBメモリは原則として使用できませんので注意が必要です。
このメディアを登記申請時に法務局へ提出することになります。
自分で作成する場合の総費用は、初期投資を含めて1万5千円から3万円程度となりますが、一度環境を整えれば将来的に他の電子申請にも活用できるというメリットがあります。
専門家に依頼する方法
電子定款の作成を専門家に依頼する方法も有効な選択肢です。
特に司法書士や行政書士に依頼すれば、定款作成から会社設立登記まで一貫してサポートを受けられます。
専門家に依頼するメリットは複数あります。
まず、電子定款作成に必要な機器やソフトウェアを自分で購入する必要がありません。
専門家は既に電子定款作成環境を整えているため、依頼者側で準備するものは最小限で済みます。
また、定款の記載内容についても専門的なアドバイスを受けられます。
事業目的の適切な表現、将来の事業展開を見据えた条項の設定、社員間のトラブルを防ぐための規定など、経験豊富な専門家ならではの視点で確認してもらえます。
| 依頼先 | 対応範囲 | 費用目安 |
|---|---|---|
| 司法書士 | 定款作成、電子定款化、登記申請まで一貫対応 | 5万円~10万円 |
| 行政書士 | 定款作成、電子定款化(登記申請は別途司法書士へ) | 3万円~6万円 |
| オンライン会社設立サービス | 定款作成支援、電子定款化、各種手続きサポート | 0円~5万円(プランにより異なる) |
近年では、オンラインで完結する会社設立サービスも充実してきました。
これらのサービスでは、質問に答えていくだけで定款が自動作成され、電子定款化も含めて手続きをサポートしてもらえます。
費用も比較的リーズナブルで、専門家への直接依頼よりも安価な場合が多くなっています。
専門家に依頼する際の注意点として、会社設立後の税務や労務についてもサポートが必要かどうかを事前に確認しておくことが重要です。
税理士や社会保険労務士と提携している事務所であれば、設立後の顧問契約も含めて総合的なサポートを受けられる可能性があります。
また、複数の専門家から見積もりを取ることもおすすめします。
サービス内容と料金を比較検討し、自分のニーズに最も合った依頼先を選択しましょう。
単に安さだけで選ぶのではなく、対応の丁寧さやアフターフォローの充実度も重要な判断基準となります。
電子定款の作成方法は、自分で作成する場合と専門家に依頼する場合でそれぞれメリットとデメリットがあります。
自分のスキルレベル、時間的余裕、予算などを総合的に考慮して、最適な方法を選択することが合同会社設立成功への第一歩となります。
合同会社の定款作成で注意すべきポイント

合同会社の定款を作成する際には、法的要件を満たすだけでなく、将来的な事業運営を見据えた内容にすることが重要です。
ここでは、定款作成時に特に注意すべき重要なポイントについて詳しく解説します。
事業目的は具体的かつ適法に
事業目的の記載は、会社が行える事業範囲を定める重要な項目です。
定款に記載されていない事業は原則として行うことができないため、慎重に検討する必要があります。
事業目的を記載する際の具体的な注意点は以下の通りです。
| 注意項目 | 内容 |
|---|---|
| 明確性 | 第三者が読んでも事業内容が理解できる表現にする |
| 適法性 | 法令に違反する事業や公序良俗に反する事業は記載できない |
| 営利性 | 営利を目的とする事業である必要がある |
| 具体性 | 抽象的すぎる表現は避け、具体的な事業内容を記載する |
将来的に事業を拡大する可能性がある場合は、「前各号に附帯または関連する一切の事業」という包括的な文言を最後に加えることで、柔軟性を持たせることができます。
ただし、あまりに多くの事業目的を羅列すると、会社の専門性が不明確になり、取引先からの信頼性が低下する可能性もあるため、バランスを考えることが大切です。
また、許認可が必要な事業を行う場合は、許認可申請時に求められる表現で記載する必要があります。
建設業、飲食業、不動産業、人材派遣業など、許認可事業を予定している場合は、事前に監督官庁に確認することをおすすめします。
社員間の取り決めを明確に
合同会社では、社員間の権利義務関係を定款で明確に定めることが非常に重要です。
株式会社と異なり、合同会社は社員同士の人的信頼関係を基礎とした組織であるため、社員間のルールを明確にしておかないと将来的なトラブルの原因となる可能性があります。
特に以下の事項については、定款に明記しておくことが推奨されます。
- 社員の加入と退社に関する手続き
- 社員の責任範囲と権限
- 社員の競業避止義務
- 秘密保持義務
- 紛争解決の方法
複数の社員で設立する場合、設立時には良好な関係であっても、事業の進行に伴い意見の相違が生じることは珍しくありません。
定款に明確なルールを定めておくことで、予防的にトラブルを回避することができます。
また、社員の死亡時や退社時の持分の取扱いについても、あらかじめ定めておくことが重要です。
相続人への承継を認めるのか、他の社員が買い取るのかなど、具体的な手続きを定款に記載しておくことで、突発的な事態にも対応できます。
業務執行社員と代表社員の設定
合同会社では、全社員が業務執行権限を持つのが原則ですが、定款で業務執行社員を定めることで、業務執行の権限を特定の社員に限定することができます。
業務執行社員と代表社員の設定については、以下の点に注意が必要です。
| 区分 | 役割 | 設定方法 |
|---|---|---|
| 業務執行社員 | 会社の業務執行に関する意思決定を行う | 定款で定める、または社員の互選で選任する |
| 代表社員 | 会社を代表して対外的な取引を行う | 業務執行社員が複数いる場合に定款または互選で定める |
| 業務執行社員でない社員 | 出資のみを行い、業務執行には関与しない | 業務執行社員を定めた場合、他の社員は自動的にこれに該当 |
業務執行社員を定めることで、意思決定の迅速化や経営の効率化を図ることができます。
特に出資者が多い場合や、積極的に経営に関与しない投資家的な社員がいる場合には、業務執行社員を限定することが有効です。
代表社員については、複数名を置くことも可能です。
その場合、各自が単独で代表権を行使できる「各自代表」とするか、複数名の共同でなければ代表権を行使できない「共同代表」とするかを定款で定めることができます。
取引の安全性と意思決定の慎重性を考慮して、適切な形態を選択する必要があります。
利益配分ルールの設定
合同会社の大きな特徴の一つが、利益配分を出資比率とは異なる割合で自由に定めることができる点です。
この柔軟性を活かすためには、定款で明確な利益配分ルールを定めておくことが不可欠です。
利益配分に関する定款の記載では、以下の点を明確にする必要があります。
- 各社員への利益配分の割合または計算方法
- 利益配分の時期と方法
- 損失の負担割合
- 内部留保の方針
例えば、資金を多く出資した社員と、実際の業務に従事する社員がいる場合、業務への貢献度に応じて利益配分を調整することができます。
出資比率が30%の社員に利益の50%を配分するといった柔軟な設定が可能です。
| 配分方法 | 特徴 | 適している場合 |
|---|---|---|
| 出資比率に応じた配分 | シンプルで分かりやすい | 社員の役割が同等の場合 |
| 定額配分 | 各社員に一定額を配分 | 少額の利益を平等に分ける場合 |
| 業績連動配分 | 各社員の貢献度に応じて配分 | 役割分担が明確な場合 |
| 複合型配分 | 複数の基準を組み合わせた配分 | 公平性と柔軟性の両立を図る場合 |
ただし、出資比率と利益配分比率を大きく乖離させる場合は、社員間で十分に合意を形成し、その理由や根拠を明確にしておくことが重要です。
後々の紛争を避けるため、なぜそのような配分にしたのかを議事録などに残しておくことも推奨されます。
また、損失の負担についても定款で定めることができます。
定めがない場合は出資比率に応じて負担することになりますが、特定の社員の負担を軽減するなどの取り決めも可能です。
将来の事業展開を見据えた記載
定款は会社設立後も変更できますが、変更には社員全員の同意が必要となり、登記事項の変更には登録免許税などのコストもかかります。
そのため、設立時の定款作成段階で将来の事業展開を十分に見据えた内容にしておくことが重要です。
将来を見据えた定款作成のポイントは以下の通りです。
まず、事業目的については、現在行う予定の事業だけでなく、将来的に展開する可能性のある関連事業も含めて記載しておくことを検討します。
ただし、あまりに広範囲の事業目的を記載すると会社の方向性が不明確になるため、中核となる事業とその周辺事業に絞ることが現実的です。
本店所在地については、具体的な番地まで定款に記載する方法と、最小行政区画(市区町村)までの記載にとどめる方法があります。
後者の場合、同一市区町村内での移転であれば定款変更が不要となるため、将来的な事務所移転の可能性がある場合は、柔軟性を持たせた記載を検討すると良いでしょう。
| 記載内容 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 番地まで記載 | 所在地が明確 | 移転時に定款変更が必要 |
| 市区町村まで記載 | 同一市区町村内の移転は定款変更不要 | 別途、本店所在地を決定する必要がある |
社員の加入や退社に関するルールも、将来を見据えて定めておくべき重要事項です。
事業が成長する過程で新たな社員を迎え入れる可能性や、既存社員が退社する可能性を想定し、その際の手続きや条件を明確にしておくことで、スムーズな組織変更が可能になります。
また、事業承継や後継者への引き継ぎを見据えて、社員の地位の相続に関する規定を設けることも検討に値します。
相続を認める場合の条件や、認めない場合の持分の買取方法などを定めておくことで、将来的な混乱を防ぐことができます。
決算期の設定についても、事業の特性や取引先の決算期、税務上の有利性などを考慮して決定します。
一度設定した決算期は変更可能ですが、変更には手続きとコストが必要となるため、慎重に検討することが大切です。
定款の変更手続きと費用

合同会社を設立した後も、事業の成長や状況の変化に応じて定款を変更する必要が生じることがあります。
ここでは、定款変更の具体的な手続きや必要な費用について詳しく解説します。
定款変更が必要な場合
合同会社の定款変更が必要となる主なケースは以下の通りです。
商号や本店所在地を変更する場合は、定款変更と登記の両方が必要になります。
事業の拡大やブランド戦略の見直しにより商号を変更することや、オフィスの移転により本店所在地が変わる場合がこれに該当します。
事業目的を追加・変更する場合も定款変更が必要です。新規事業への進出や事業内容の拡大に伴い、既存の事業目的では対応できなくなった際に変更手続きを行います。
この場合、登記申請も必要となります。
社員の加入・脱退があった場合にも定款変更が必要です。
合同会社では社員が出資者であり経営者でもあるため、社員構成の変更は重要な事項となります。
出資額や持分割合の変更を伴う場合は、特に慎重な手続きが求められます。
資本金の増減を行う場合も定款変更の対象となります。
事業拡大のための増資や、財務状況の改善のための減資を行う際には、定款に記載された資本金の額を変更する必要があります。
業務執行社員や代表社員の変更を行う場合にも定款変更が必要です。
経営体制の見直しや世代交代などで、業務執行の権限を持つ社員や会社を代表する社員を変更する際に手続きを行います。
事業年度の変更を行う場合も定款変更が必要となります。
税務上の理由や事業の繁閑期を考慮して事業年度を変更することがあります。
定款変更の決議方法
合同会社における定款変更は、原則として社員全員の同意が必要とされています。
これは株式会社とは大きく異なる点であり、会社法第637条に規定されています。
定款変更の決議を行う際の具体的な手順は以下の通りです。
まず、定款変更の提案を行います。
業務執行社員または代表社員が、変更の必要性と変更内容について他の社員に説明し、議題として提案します。
変更内容を明確にした変更案を書面で用意することが望ましいでしょう。
次に、全社員による協議と同意取得を行います。
社員総会を開催するか、または書面や電磁的方法により、全社員の意見を聴取します。
一人でも反対する社員がいる場合は、原則として定款変更はできません。
ただし、定款に別段の定めがある場合は、その定めに従うことができます。
例えば、「定款変更は社員の過半数の同意により行うことができる」などの規定を定款に記載しておくことで、全員一致でなくても変更が可能になります。
このような規定を設ける場合は、会社設立時または後の定款変更時に明記しておく必要があります。
社員全員の同意が得られたら、定款変更の議事録を作成します。
議事録には、変更の日時、場所、出席社員、議題、決議内容などを記載し、出席した社員全員が署名または記名押印します。
定款変更の効力発生時期は、原則として社員全員の同意が得られた時点です。
ただし、登記事項に関する変更の場合は、登記が完了した時点で第三者に対抗できるようになります。
| 決議方法 | 要件 | 特徴 |
|---|---|---|
| 原則(法定) | 社員全員の同意 | 会社法第637条に規定される基本原則 |
| 定款で別段の定めがある場合 | 定款に記載された要件(例:過半数、3分の2以上など) | 柔軟な意思決定が可能になるが、設立時または事前の定款変更で規定が必要 |
| 書面による決議 | 社員全員の書面による同意 | 社員総会を開催せずに決議できる |
| 電磁的方法による決議 | 社員全員の電子メール等による同意 | 遠隔地にいる社員がいる場合に有効 |
登記が必要な変更と不要な変更
定款変更を行った場合、その内容によって登記申請が必要なものと不要なものがあります。
登記が必要な変更事項は、法務局への登記申請を行わなければ、第三者に対して変更の効力を主張できません。
登記が必要な主な定款変更事項は以下の通りです。
商号の変更は登記事項です。
会社名を変更する場合は、定款変更後2週間以内に本店所在地を管轄する法務局に変更登記を申請する必要があります。
商号変更登記の登録免許税は3万円です。
本店所在地の変更も登記事項です。
管轄法務局内での移転の場合は登録免許税3万円、管轄外への移転の場合は旧所在地で3万円、新所在地で3万円の合計6万円が必要となります。
事業目的の変更も登記が必要です。
新たな事業を追加する場合や既存の目的を変更・削除する場合には、変更登記を申請します。
登録免許税は3万円です。
資本金の額の変更も登記事項です。
増資または減資を行った場合には、変更登記が必要となります。
登録免許税は、資本金の増加額の1,000分の7(最低3万円)です。
社員の氏名または名称、住所の変更も登記事項です。
社員の構成に変更があった場合や、既存社員の住所が変わった場合には登記申請を行います。
登録免許税は1万円です。
業務執行社員や代表社員の変更も登記が必要です。
経営体制の変更に伴いこれらの役職に変更があった場合は、変更登記を申請します。登録免許税は1万円です。
一方、登記が不要な定款変更事項もあります。
これらは定款変更の決議と定款本文の修正のみで完了します。
事業年度の変更は登記不要です。
決算期を変更する場合でも、登記申請は必要ありません。
ただし、税務署や都道府県税事務所、市区町村役場への異動届の提出は必要です。
社員の出資割合の変更(資本金の額に変更がない場合)も登記不要です。
社員間での持分の譲渡などで出資割合が変わっても、資本金の総額に変更がなければ登記は必要ありません。
利益配分の方法や割合の変更も登記不要です。
定款で定める利益の分配ルールを変更する場合でも、登記申請は不要です。
社員総会の招集方法や決議要件の変更も登記不要です。
定款自治の範囲で定める手続き的な事項の変更は、登記の対象外です。
| 変更事項 | 登記の要否 | 登録免許税 | 申請期限 |
|---|---|---|---|
| 商号 | 必要 | 3万円 | 変更後2週間以内 |
| 本店所在地(管轄内) | 必要 | 3万円 | 変更後2週間以内 |
| 本店所在地(管轄外) | 必要 | 6万円(旧3万円+新3万円) | 変更後2週間以内 |
| 事業目的 | 必要 | 3万円 | 変更後2週間以内 |
| 資本金の額 | 必要 | 増加額の0.7%(最低3万円) | 変更後2週間以内 |
| 社員の氏名・住所 | 必要 | 1万円 | 変更後2週間以内 |
| 業務執行社員・代表社員 | 必要 | 1万円 | 変更後2週間以内 |
| 事業年度 | 不要 | - | - |
| 出資割合(資本金不変) | 不要 | - | - |
| 利益配分方法 | 不要 | - | - |
定款変更にかかる費用
合同会社の定款変更にかかる費用は、変更内容や手続き方法によって異なります。
費用の内訳を理解しておくことで、適切な予算計画を立てることができます。
登記申請が必要な場合の費用は、主に登録免許税と専門家への報酬に分けられます。
登録免許税は、変更する登記事項によって金額が異なります。
前述の表の通り、商号変更は3万円、本店移転は管轄内で3万円、管轄外で6万円、事業目的変更は3万円、資本金変更は増加額の0.7%(最低3万円)、社員や役員の変更は1万円となっています。
複数の登記事項を同時に変更する場合、それぞれの登録免許税が加算されます。
例えば、商号変更と事業目的変更を同時に行う場合は、3万円+3万円=6万円の登録免許税が必要です。
自分で登記申請を行う場合は、登録免許税以外の費用はほとんどかかりません。
ただし、登記申請書の作成や必要書類の準備に時間と労力がかかります。
司法書士に依頼する場合の報酬は、変更内容や事務所によって異なりますが、一般的な相場は以下の通りです。
| 依頼内容 | 司法書士報酬の相場 | 登録免許税 | 合計費用の目安 |
|---|---|---|---|
| 商号変更 | 2万円~4万円 | 3万円 | 5万円~7万円 |
| 本店移転(管轄内) | 2万円~4万円 | 3万円 | 5万円~7万円 |
| 本店移転(管轄外) | 4万円~6万円 | 6万円 | 10万円~12万円 |
| 事業目的変更 | 2万円~4万円 | 3万円 | 5万円~7万円 |
| 資本金変更 | 3万円~5万円 | 増加額の0.7%(最低3万円) | 6万円~(増加額により変動) |
| 社員・役員変更 | 1万円~3万円 | 1万円 | 2万円~4万円 |
| 複数事項の同時変更 | 5万円~10万円 | 変更事項により変動 | 8万円~(内容により変動) |
司法書士報酬には、定款変更の議事録作成支援、登記申請書類の作成、法務局への申請代行などが含まれます。
複雑な変更や複数の変更を同時に行う場合は、専門家に依頼することで手続きの正確性と効率性が高まります。
登記申請が不要な定款変更の費用は、基本的に登録免許税がかからないため、自分で手続きを行えば費用はほとんど発生しません。
ただし、定款変更の議事録作成や新しい定款の製本などの実費が数千円程度かかる場合があります。
行政書士に定款変更の相談や書類作成を依頼する場合は、1万円~3万円程度の報酬が一般的です。
登記申請が不要な変更であっても、適切な手続きを踏むことが重要なため、不安がある場合は専門家に相談することをお勧めします。
その他、定款変更に伴って必要となる可能性がある費用として、以下のようなものがあります。
定款の再製本費用は、変更後の定款を正式に製本する場合に数千円程度かかります。
電子定款の場合は、PDF形式での保存となるため、この費用は不要です。
税務署等への届出書類の作成費用は、事業年度の変更などで税務署への届出が必要な場合、税理士に依頼すると1万円~2万円程度の費用がかかることがあります。
印鑑証明書の取得費用は、登記申請時に必要な場合があり、1通あたり数百円かかります。
複数の社員の印鑑証明書が必要な場合は、その分の費用が加算されます。
定款変更の費用を抑えるためには、複数の変更事項がある場合はまとめて手続きを行うこと、自分でできる部分は自分で行い専門家への依頼範囲を最小限にすること、電子定款を活用することなどが有効です。
ただし、費用削減を優先するあまり手続きに誤りがあると、後から修正するための追加費用や時間がかかる可能性があるため、慎重に判断することが大切です。
よくある質問と回答

合同会社の定款に関するQ&A
合同会社の定款作成に際して、多くの方が疑問に感じる点について、実務的な視点から回答します。
これから合同会社を設立される方は、ぜひ参考にしてください。
Q1. 合同会社の定款は必ず作成しなければなりませんか
Q2. 合同会社の定款は公証人の認証が必要ですか
Q3. 定款は紙で作成すべきですか、電子定款にすべきですか
Q4. 定款の作成は自分でできますか、専門家に依頼すべきですか
| 状況 | 推奨 | 理由 |
|---|---|---|
| 複数の社員がいる場合 | 専門家に依頼 | 利益配分や業務執行の取り決めが複雑になるため |
| 特殊な事業を行う場合 | 専門家に依頼 | 許認可との関連で事業目的の記載に注意が必要なため |
| 将来の資金調達を考えている場合 | 専門家に依頼 | 株式会社への組織変更を見据えた記載が必要なため |
| 一人で設立し、シンプルな事業の場合 | 自分で作成可能 | 定型的な内容で十分対応できるため |
Q5. 定款に押す印鑑は実印でなければなりませんか
Q6. 定款の原本は何通必要ですか
Q7. 事業目的は何個まで記載できますか
Q8. 定款に記載した事業目的以外の事業はできませんか
Q9. 社員の氏名や住所が変わったら定款も変更が必要ですか
Q10. 資本金の額は定款にどのように記載すればよいですか
Q11. 合同会社から株式会社に変更する場合、定款はどうなりますか
Q12. 定款に記載する本店所在地はどこまで詳しく書くべきですか
Q13. 合同会社の定款に決算期を記載する必要がありますか
Q14. 定款の作成日と設立日は同じでなければなりませんか
Q15. 定款の保管方法に決まりはありますか
Q16. 定款に記載する社員と従業員は同じですか
Q17. 定款の記載内容に誤りがあった場合はどうすればよいですか
Q18. 一人で設立する場合の定款作成の注意点はありますか
まとめ
合同会社の定款は会社の基本ルールを定める重要な書類であり、株式会社と異なり公証人の認証が不要という大きな特徴があります。
この認証不要により、定款作成にかかる時間とコストを大幅に削減できるため、スピーディーかつ低コストでの会社設立が可能です。
定款には絶対的記載事項として、商号・事業目的・本店所在地・社員の氏名または名称と住所・社員の出資目的とその価額または評価基準の5項目を必ず記載する必要があります。
これらが一つでも欠けると定款自体が無効となるため注意が必要です。
電子定款を選択すれば、書面定款で必要な収入印紙代4万円を節約できます。
初期費用を抑えたい場合は、電子定款での作成を検討する価値があります。
ただし、電子署名のための機器やソフトウェアの準備が必要になるため、自分で作成するか専門家に依頼するかを判断しましょう。
定款作成時には、事業目的の適切な記載、社員間の権利義務の明確化、業務執行社員と代表社員の設定、利益配分ルールなど、将来のトラブルを防ぐための慎重な検討が求められます。
特に複数の社員で設立する場合は、後々の紛争を避けるために詳細な取り決めを定款に盛り込むことが重要です。
定款は会社設立後も変更が可能ですが、変更内容によっては登記申請が必要となり、登録免許税などの費用が発生します。
そのため、設立時に将来の事業展開も見据えた内容にしておくことで、無駄な変更手続きを避けることができます。
合同会社の定款作成は株式会社に比べて手続きが簡素ですが、だからこそ記載内容の正確性と将来を見据えた慎重な検討が必要です。
不安がある場合は、司法書士や行政書士などの専門家に相談することで、適切な定款を作成し、スムーズな会社設立を実現できます。