合同会社は、専門家に頼らず自分で設立することが可能です。
この記事では、設立に必要な準備、定款作成から登記申請までの具体的な手順、費用を抑える方法、そして注意点まで詳しく解説します。
専門家へ依頼する場合との違いも比較し、メリット・デメリットを理解した上で、ご自身に最適な設立方法を見つける手助けをします。
手続きの流れや必要書類も網羅しています。
合同会社設立は自分でできるのか?専門家依頼との違い
結論から申し上げると、合同会社の設立手続きは、専門家に依頼せず自分自身で行うことが可能です。
株式会社の設立と比較して、合同会社は設立手続きが比較的シンプルであり、定款認証が不要であるなど、個人でも取り組みやすい点が特徴です。
実際に、多くの起業家がコスト削減や会社設立プロセスへの理解を深める目的で、ご自身で設立手続きを進めています。
しかし、自分で設立する場合と、司法書士や行政書士、税理士といった専門家に依頼する場合では、それぞれ異なる特徴があります。
どちらの方法がご自身の状況に適しているかを判断するために、まずは両者の違いを理解することが重要です。
主な違いは、「設立にかかる費用」「手続きに要する時間と手間」「書類作成の正確性」「設立後のサポート」などが挙げられます。
以下の表で、それぞれの特徴を比較してみましょう。
| 比較項目 | 自分で設立する場合 | 専門家に依頼する場合 |
|---|---|---|
| 設立費用 | 専門家への報酬が不要なため、費用を最も安く抑えられる(登録免許税6万円+その他実費)。電子定款を利用すれば印紙代4万円も節約可能。 | 登録免許税などの実費に加え、専門家への報酬(数万円〜十数万円程度)が発生する。ただし、設立手数料無料のサービスを提供している事務所もある(税務顧問契約などが条件の場合が多い)。 |
| 時間と手間 | 定款作成、必要書類の準備、法務局への申請など、すべての手続きを自分で行うため、相応の時間と手間がかかる。情報収集や学習の時間も必要。 | 面倒な書類作成や申請手続きの大部分を代行してもらえるため、時間と手間を大幅に削減できる。事業準備に集中できる。 |
| 専門性・確実性 | 書類の不備や記載漏れのリスクがある。手続きに慣れていない場合、修正や再申請が必要になる可能性も。定款の内容が事業実態や将来の展望に合わない可能性もある。 | 専門家が法的な知識に基づいて正確な書類を作成・申請するため、手続きがスムーズに進み、不備のリスクが低い。事業内容に応じた適切な定款作成のアドバイスも受けられる。 |
| 設立後のサポート | 設立後の税務署への届出や社会保険手続きなども自分で行う必要がある。手続き漏れや不明点が生じる可能性がある。 | 設立後の各種届出や、税務・労務に関する相談、記帳代行など、継続的なサポートを受けられる場合がある(別途契約が必要な場合が多い)。特に税理士に依頼した場合、税務顧問として事業運営をサポートしてもらえる。 |
専門家に依頼する場合、主に司法書士、行政書士、税理士が候補となります。
それぞれの専門分野は以下の通りです。
- 司法書士: 会社設立登記の申請代理を独占業務としています。登記手続きのプロフェッショナルであり、確実な設立登記を任せられます。
- 行政書士: 定款作成の代理や、事業に必要な許認可申請のサポートを得意としています。許認可が必要な事業を始める場合に頼りになります。
- 税理士: 設立後の税務届出や税務相談、顧問契約を主に行います。設立段階から税務面でのアドバイスを受けたい場合や、設立後の経理・税務サポートを重視する場合に適しています。設立手続き自体は提携の司法書士が行うケースが多いです。
このように、自分で設立する場合と専門家に依頼する場合では、費用、時間、確実性、サポートの面で大きな違いがあります。
費用を最優先で抑えたい、会社設立のプロセスを学びたいという方は自分で設立することにメリットを感じるでしょう。
一方で、時間的な余裕がない、手続きに不安がある、設立後のサポートも受けたいという方は専門家への依頼を検討する価値があります。
ご自身の状況や優先順位に合わせて、最適な方法を選択しましょう。
自分で合同会社を設立するメリットとデメリット

合同会社の設立手続きは、株式会社に比べて簡略化されている部分もありますが、それでも専門的な知識が求められる場面は少なくありません。
専門家(司法書士や行政書士など)に依頼せず、すべて自分自身の手で設立手続きを進めることには、メリットとデメリットの両方が存在します。
どちらの方法がご自身の状況に適しているか、慎重に検討しましょう。
ここでは、自分で合同会社を設立する場合の具体的なメリットとデメリットを詳しく解説します。
自分で設立するメリット
まずは、自分で合同会社を設立する主なメリットを2つご紹介します。
1.設立費用を安く抑えられる
最大のメリットは、設立にかかる費用を大幅に削減できる点です。
専門家に設立代行を依頼した場合、一般的に数万円から十数万円程度の報酬が発生します。
この専門家報酬が一切かからないため、純粋に法定費用(登録免許税など)のみで会社を設立できます。
合同会社設立に必要な主な費用は以下の通りです。
- 登録免許税: 最低6万円(資本金の額 × 0.7%。6万円に満たない場合は6万円)
- 定款用収入印紙代: 4万円(電子定款の場合は不要)
- その他:(印鑑作成費用、印鑑証明書取得費用など)
専門家に依頼すると、これらの法定費用に加えて代行手数料がかかります。
例えば、司法書士に登記申請まで依頼すると、5万円〜10万円程度が相場と言われています。
行政書士に定款作成のみを依頼する場合でも数万円の費用が発生します。
これらの専門家報酬がゼロになるのは、特に初期費用を抑えたい創業者にとって大きな魅力です。
さらに、後述する電子定款を利用すれば、紙の定款に必要な収入印紙代4万円も節約できるため、最低6万円の登録免許税のみで設立することも可能になります。
2.会社設立手続きの知識が身につく
自分で設立手続きを経験することで、会社設立に関する一連の流れや必要な書類、関連法規について深く理解することができます。
定款の作成を通じて会社の基本的なルール(商号、目的、本店所在地、資本金、役員など)を具体的に定め、登記申請書類を作成する過程で商業登記法に触れることになります。
具体的には、以下のような知識やスキルが身につきます。
- 定款の絶対的記載事項・相対的記載事項・任意的記載事項の理解
- 登記申請に必要な書類の種類と作成方法
- 資本金の払い込み手順と証明書類の作成方法
- 法務局での登記申請手続きの流れ
- 会社設立後に必要となる税務署や年金事務所への届出
これらの知識は、会社設立時だけでなく、設立後の会社運営においても非常に役立ちます。
例えば、将来的に定款変更が必要になった場合や、役員変更、本店移転などの登記手続きが発生した場合でも、基本的な流れを理解しているためスムーズに対応しやすくなります。
また、どのような手続きで専門家のサポートが必要になるかを見極める判断力も養われます。
自分で設立するデメリット
一方で、自分で合同会社を設立するには、いくつかのデメリットや注意すべき点も存在します。
1.時間と手間がかかる
会社設立手続きには、情報収集から書類作成、法務局への申請、設立後の諸手続きまで、多くの時間と手間がかかります。
特に初めて会社を設立する場合、どの情報を参考にすれば良いのか、どのような書類を準備すれば良いのかを調べるだけでも相当な時間を要する可能性があります。
具体的に、以下のような作業に時間と労力が必要です。
- 設立する会社の基本事項(商号、目的、本店所在地など)の決定と調査
- 定款の作成(記載事項の検討、法的な整合性の確認)
- 登記申請書類一式の作成
- 必要書類(印鑑証明書など)の収集
- 資本金の払い込みと証明書類の準備
- 法務局への申請(窓口、郵送、オンライン)
- 設立後の税務署、都道府県税事務所、市町村役場、年金事務所などへの届出
本業の準備や営業活動と並行してこれらの作業を行うのは、大きな負担となる可能性があります。
特に、手続きに慣れていない場合は、想定以上に時間がかかり、事業開始のスケジュールに遅れが生じるリスクも考慮しなければなりません。
2.書類作成でミスをする可能性がある
定款や登記申請書類の作成には、会社法や商業登記法などの専門的な知識が求められます。
記載事項に漏れがあったり、誤った内容を記載したりすると、法務局で受理されなかったり、補正(修正)を求められたりする可能性があります。
特に注意が必要なのは以下のような点です。
- 定款の記載事項: 絶対的記載事項の漏れ、事業目的の表現が不明確、違法な内容の記載など。
- 登記申請書類: 会社名や住所の誤記、必要書類の添付漏れ、押印の誤りや漏れなど。
書類に不備があると、法務局から連絡があり、修正して再提出する必要があります。これにより、設立手続きが大幅に遅延する可能性があります。
場合によっては、何度も法務局に足を運んだり、郵送でやり取りしたりする必要が生じ、余計な時間と労力がかかってしまいます。
また、定款の内容、特に事業目的や社員構成、利益配分に関する規定などは、後々の会社運営や税務にも影響を与えるため、安易な作成は避けるべきです。
3.設立後の手続きで困る可能性がある
会社設立は登記申請が完了すれば終わりではありません。
設立後には、税務署、都道府県税事務所、市町村役場、年金事務所など、関係各所への届出が義務付けられています。
これらの手続きを怠ると、税制上の優遇措置(青色申告など)を受けられなくなったり、過料(罰金)が科されたりするリスクがあります。
主な設立後の手続きには以下のようなものがあります。
- 法人設立届出書(税務署、都道府県税事務所、市町村役場)
- 青色申告の承認申請書(税務署)
- 給与支払事務所等の開設届出書(税務署)
- 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書(税務署)
- 健康保険・厚生年金保険新規適用届(年金事務所)
- 労働保険関係成立届(労働基準監督署)※従業員雇用時
- 雇用保険適用事業所設置届(ハローワーク)※従業員雇用時
自分で設立した場合、これらの設立後の手続きもすべて自分で行う必要があります。
どのような届出がいつまでに必要なのかを正確に把握し、適切に書類を作成・提出しなければなりません。
税務や社会保険に関する知識が不足していると、どの書類を提出すべきか、どのように記入すれば良いか分からず、手続きが滞ってしまう可能性があります。
専門家に依頼すれば、これらの設立後手続きのサポートやアドバイスを受けられる場合もありますが、自分で行う場合はすべて自己責任となります。
メリットとデメリットをまとめると以下のようになります。
| メリット | デメリット | |
|---|---|---|
| 費用面 | 専門家報酬がかからず、設立費用を大幅に抑えられる。電子定款なら印紙代4万円も節約可能。 | – (費用面でのデメリットは特にないが、時間的コストはかかる) |
| 知識・経験面 | 会社設立や運営に関する知識・経験が身につく。今後の会社運営に役立つ。 | 専門知識がないと、書類作成ミスや手続き漏れのリスクがある。 |
| 時間・労力面 | – (時間・労力面でのメリットは特にない) | 情報収集や書類作成、各種手続きに多くの時間と手間がかかる。本業に支障が出る可能性も。 |
| 確実性・スピード面 | – (確実性・スピード面でのメリットは特にない) | 書類不備による補正や再申請で、設立が遅れる可能性がある。設立後の手続きで困る可能性も。 |
これらのメリット・デメリットを総合的に比較検討し、ご自身の状況(時間的余裕、予算、専門知識の有無など)に合わせて、自分で設立するか、専門家に依頼するかを判断することが重要です。
合同会社を自分で設立するための準備リスト
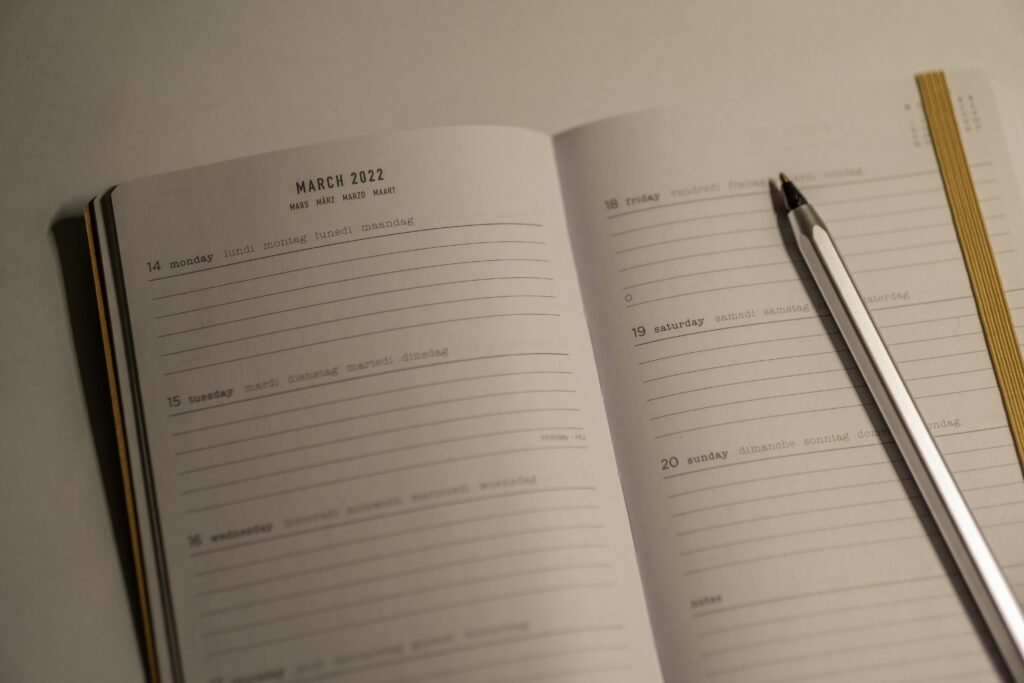
合同会社の設立手続きを自分で行うと決めたら、まず最初にやるべきことは「準備」です。
設立手続きそのものは手順に沿って進めれば完了しますが、その前段階である準備が不十分だと、手続きが滞ったり、後々思わぬトラブルに見舞われたりする可能性があります。
スムーズな会社設立と事業開始のためにも、ここで紹介する準備リストを参考に、一つひとつ着実に進めていきましょう。
設立する会社の基本事項を決める
会社の設立は、いわば新しい組織の骨格を作り上げることです。
まずは、その骨格となる会社の基本的なルールや情報を決定する必要があります。
これらの基本事項は、会社の憲法ともいえる「定款(ていかん)」に記載される非常に重要な項目です。
後から変更することも可能ですが、手間や費用がかかる場合もあるため、設立時点で慎重に検討しましょう。
会社の商号(名前)
会社の顔となるのが「商号」です。覚えやすく、事業内容がイメージできるような、魅力的な名前を考えましょう。
ただし、商号を決める際にはいくつかのルールがあります。
- 使用できる文字:漢字、ひらがな、カタカナ、ローマ字(大文字・小文字)、アラビア数字(0~9)、一部の記号(「&」「’」「,」「-」「.」「・」)が使用できます。スペースも単語を区切る場合に限り使用可能です。
- 「合同会社」の文字:商号の中に必ず「合同会社」という文字を含める必要があります。入れる位置は、「合同会社〇〇」「〇〇合同会社」のように、商号の前でも後でも構いません。
- 同一商号・同一本店の禁止:既に登記されている会社と全く同じ商号で、かつ本店所在地も同じ場所では登記できません。
- 不正競争防止法:有名企業や著名なブランドと同一または類似した商号を使用すると、不正競争防止法に抵触し、損害賠償請求などを受けるリスクがあります。
希望する商号が使えるかどうかは、事前に法務局の「オンライン登記情報検索サービス」やインターネット検索で類似商号がないか調査することを強くおすすめします。
また、将来的にウェブサイトを開設することも見越して、希望する商号に関連するドメイン名が取得可能かどうかも同時に確認しておくと良いでしょう。
事業目的
事業目的は、その会社が「どのような事業を行うのか」を具体的に示すものです。
定款に記載された事業目的の範囲内でしか、会社は事業活動を行うことができません。
また、許認可が必要な事業を行う場合は、その許認可の要件を満たす事業目的を正確に記載する必要があります。
事業目的を記載する際は、以下の点に注意しましょう。
- 適法性:法律に違反する内容や公序良俗に反する内容は記載できません。
- 明確性:誰が見ても事業内容を具体的に理解できるよう、明確な言葉で記載します。曖昧な表現は避けましょう。
- 営利性:会社は営利を目的とする法人ですので、ボランティア活動など営利性のない目的は記載できません。
設立時に行う事業だけでなく、将来的に展開する可能性のある事業も、あらかじめ記載しておくことをおすすめします。
後から事業目的を追加するには、定款変更の手続きと登記変更が必要となり、費用(登録免許税3万円)と手間がかかるためです。
ただし、あまりにも多くの事業目的を羅列すると、何の会社か分かりにくくなる可能性もあるため、バランスを考慮しましょう。
◆ 記載例
- 飲食店の経営
- 経営コンサルティング業務
- ウェブサイトの企画、制作及び運営
- 上記各号に附帯関連する一切の事業
最後の「上記各号に附帯関連する一切の事業」という一文を入れておくと、主たる事業に関連する業務を幅広くカバーできます。
本店所在地
本店所在地は、会社の「住所」にあたるものです。
どこを本店所在地とするかは、自由に決めることができます。
主な選択肢としては、以下のような場所が考えられます。
| 選択肢 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 自宅 | 家賃がかからない、通勤時間がない | プライバシーの問題、事業用と認識されにくい場合がある、賃貸の場合は規約確認が必要 |
| 賃貸オフィス | 社会的信用度が高い、事業スペースを確保できる | 家賃や保証金などのコストがかかる |
| バーチャルオフィス | 低コストで都心などの住所を利用できる | 実際の作業スペースはない、許認可の種類によっては認められない場合がある |
| シェアオフィス・コワーキングスペース | 比較的低コスト、他の事業者との交流が生まれる可能性 | プライバシー確保が難しい場合がある、登記可否の確認が必要 |
賃貸物件やシェアオフィスなどを本店所在地とする場合は、必ず契約前に法人登記が可能かどうか、事業利用が規約で認められているかを確認してください。
自宅を本店所在地とする場合も、マンションの管理規約などで事業利用や法人登記が禁止されていないか確認が必要です。
定款への記載方法は、最小行政区画(例:「東京都千代田区」)まで記載する方法と、地番まで含めた詳細な住所(例:「東京都千代田区〇〇一丁目一番一号」)を記載する方法があります。
最小行政区画までの記載にしておくと、同じ市区町村内で移転した場合、定款変更が不要になるというメリットがあります。
ただし、登記申請時には詳細な住所が必要となります。
資本金の額
資本金は、会社設立時に社員(出資者)が会社に払い込む資金のことです。
会社の事業活動の元手となるお金であり、会社の体力や信用度を示す指標の一つにもなります。
会社法上は1円からでも合同会社を設立できますが、あまりに少額だと会社の信用力が低く見られたり、設立後すぐに資金ショートを起こしたりするリスクがあります。
資本金の額を決める際は、以下の点を考慮しましょう。
- 設立当初に必要な費用:事務所の賃料、備品の購入費、仕入れ費用など。
- 当面の運転資金:売上が安定するまでの数ヶ月分(一般的には3~6ヶ月程度)の運転資金(人件費、家賃、仕入れ代金など)。
- 許認可の要件:特定の事業を行う場合、許認可の取得要件として一定額以上の資本金が必要となることがあります。
- 社会的信用:取引先や金融機関からの信用を得るためには、ある程度の資本金額があった方が有利な場合があります。
これらの要素を総合的に判断し、現実的な事業計画に基づいた適切な金額を設定することが重要です。
なお、金銭だけでなく、パソコンや車、不動産などの「モノ」で出資する「現物出資」も可能です。
ただし、現物出資を行う場合は、その財産の評価額を適切に算定し、定款への記載や調査報告書の作成など、手続きが少し複雑になります。
社員(出資者)構成
合同会社における「社員」とは、一般的な意味での従業員ではなく、「出資者」のことを指します。
株式会社における株主に近い存在ですが、合同会社の社員は原則として会社の「業務執行権(=会社の業務を行う権利)」も持ちます。
つまり、出資者=経営者となるのが合同会社の基本です。
設立準備段階で、以下の点を明確にしておく必要があります。
- 誰が社員(出資者)になるのか:合同会社は1名以上で設立できます。自分一人で設立することも、複数人で設立することも可能です。
- 各社員の出資額:誰がいくら出資するのかを決めます。出資額に応じて、利益配分の割合などを定款で定めることができます。
- 業務執行社員と代表社員:社員が複数いる場合、定款で特定の社員のみを業務執行社員(実際に業務を行う社員)と定めることができます。さらに、業務執行社員の中から会社を代表する「代表社員」を定めます(株式会社の代表取締役に相当)。社員が1名の場合は、その社員が自動的に代表社員となります。
社員構成や役割分担は、会社の運営方針に直結する重要な事項です。
複数名で設立する場合は、それぞれの責任や権限、利益配分などについて、事前に十分に話し合い、定款に明記しておくことが後のトラブル防止につながります。
事業年度
事業年度とは、会社の損益計算や財産状況をまとめる「決算」を行うための期間(会計期間)のことです。
事業年度の末日から2ヶ月以内に法人税などの確定申告と納税を行う必要があります。
事業年度は自由に決めることができますが、一般的には1年間とされることが多いです(例:4月1日から翌年3月31日まで、1月1日から12月31日まで)。
事業年度の決め方には、以下のような考え方があります。
- 繁忙期を避ける:決算業務や税理士との打ち合わせが必要になるため、会社の繁忙期と決算期が重ならないように設定します。
- 消費税の免税期間を考慮する:資本金1,000万円未満で設立した場合、原則として設立1期目と2期目は消費税が免除されます(※課税売上高などの条件あり)。この免税期間を最大限活用するために、設立日からできるだけ決算期が遠くなるように設定する(例:4月設立なら3月決算)という考え方もあります。
- 資金繰りを考慮する:納税時期を考慮し、資金繰りに余裕のある時期を決算期とする考え方もあります。
設立日から1年以内に最初の決算期が到来するように設定する必要があります。
例えば、4月1日に設立した場合、事業年度を4月1日~3月31日とすれば、最初の決算は翌年の3月31日となります。
事前に用意するもの
会社の基本事項が決まったら、次は設立手続きに必要な書類やモノを具体的に準備していきます。
スムーズな手続きのためには、漏れなく早めに準備を進めることが大切です。
社員全員の印鑑証明書
合同会社の設立登記を申請する際には、原則として社員(出資者)全員の印鑑証明書が必要となります。
これは、定款の内容に同意し、社員となる意思があることを公的に証明するためです。
- 取得場所:個人の住所地を管轄する市区町村役場または出張所、マイナンバーカードがあればコンビニエンスストアのマルチコピー機でも取得可能です。
- 有効期限:法務局に提出する印鑑証明書は、発行日から3ヶ月以内のものである必要があります。取得時期に注意しましょう。
- 必要枚数:登記申請用に最低1通は必要です。その他、法人口座の開設などで必要になる場合もあるため、念のため複数枚取得しておくと安心です。
社員となる人全員に、早めに印鑑証明書の準備を依頼しましょう。
会社の実印(代表社員印)
会社の実印は、法務局に登録する会社の最も重要な印鑑です。
「代表社員印」や「法人実印」とも呼ばれます。
設立登記申請の際に、この印鑑を法務局に届け出る(印鑑届出)必要があります。今後、重要な契約書や公的機関への提出書類などに使用することになります。
- 印鑑の規定:一般的に、印面の大きさは一辺が1cmを超え、3cm以内の正方形に収まるものとされています。形状は丸いものが主流です。
- 材質や書体:特に決まりはありませんが、欠けにくく耐久性のある材質(チタン、黒水牛など)や、偽造されにくい書体(篆書体、印相体など)が好まれます。
- 作成タイミング:会社の商号が正式に決定してから作成を依頼しましょう。
- その他の印鑑:必須ではありませんが、会社の実印と合わせて、銀行印(金融機関での取引に使用)と角印(請求書や領収書など日常的な書類に使用する認印)も作成しておくと、業務上非常に便利です。実印と銀行印は、セキュリティのためにも異なる印鑑にすることをおすすめします。
印鑑は、印鑑専門店やオンラインショップなどで作成できます。
納期を確認し、登記申請に間に合うように準備しましょう。
| 印鑑の種類 | 主な用途 | 作成のポイント |
|---|---|---|
| 会社実印(代表社員印) | 設立登記、重要な契約書、官公庁への書類 | 法務局へ登録必須、欠けにくく偽造されにくいもの |
| 銀行印 | 銀行口座開設、手形・小切手の発行 | 実印とは別の印鑑にするのが安全 |
| 角印(社印) | 請求書、領収書、見積書など日常的な書類 | 認印として使用、読みやすい書体でも可 |
資本金の払込用銀行口座
設立登記の際には、定款で定めた資本金が実際に払い込まれたことを証明する書類(払込証明書)が必要になります。
この資本金を払い込むための銀行口座を準備します。
重要な点として、会社設立前はまだ法人口座を開設できません。
そのため、資本金の払込は、発起人(代表社員となる個人のケースが多い)の個人名義の銀行口座を使用します。
- 使用する口座:既存の個人口座で問題ありませんが、資本金の入金履歴を明確にするために、普段あまり使っていない口座や、この設立のために新たに開設した個人口座を利用すると、通帳のコピーなどが分かりやすくなり、後の手続きがスムーズです。
- 払込方法:定款作成日以降の日付で、各社員が出資金をその口座に振り込みます。発起人一人がまとめて振り込んでも構いません。
- 記録の保管:振り込みが完了したら、通帳の表紙、裏表紙(銀行名、支店名、口座番号、名義人が分かるページ)、そして資本金の入金が記帳されたページをコピーしておきます。これが払込証明書の添付資料となります。
どの口座に払い込むかを事前に決め、社員全員に周知しておきましょう。
合同会社を自分で設立する具体的な手順と流れ
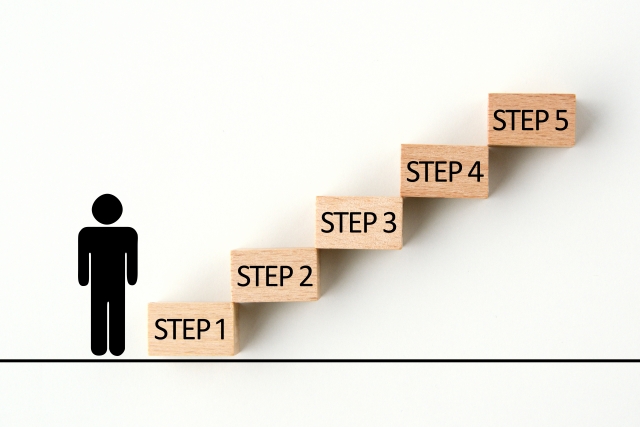
合同会社の設立は、株式会社に比べて手続きが簡略化されており、自分で行うことも十分に可能です。
ここでは、合同会社を自分で設立するための具体的な手順と流れを5つのステップに分けて詳しく解説します。
各ステップで必要な書類や注意点も確認しながら進めましょう。
ステップ1 定款を作成する
会社設立の最初のステップは、会社の基本ルールとなる「定款(ていかん)」を作成することです。
定款は会社の憲法とも言える重要な書類であり、記載漏れや不備がないように慎重に作成する必要があります。
定款の記載事項を確認する
定款に記載する事項は、必ず記載しなければならない「絶対的記載事項」、定めないと効力が生じない「相対的記載事項」、任意で記載できる「任意的記載事項」の3つに分類されます。
特に絶対的記載事項が欠けていると定款自体が無効となるため注意が必要です。
| 絶対的記載事項 | 主な内容 |
|---|---|
| 商号 | 会社名。前後に「合同会社」の文字を入れる必要があります。(例:合同会社〇〇、〇〇合同会社) |
| 事業目的 | 会社が行う事業内容。具体的かつ明確に記載し、将来行う可能性のある事業も記載しておくと良いでしょう。適法性や営利性も必要です。 |
| 本店所在地 | 会社の住所。最小行政区画(例:東京都新宿区)までの記載でも可能ですが、登記申請までには具体的な地番まで決定する必要があります。 |
| 社員の氏名及び住所 | 出資者全員の氏名と住所を記載します。 |
| 社員全員が有限責任社員であること | 合同会社の特徴である、社員が出資額までしか責任を負わない旨を明記します。 |
| 社員の出資の目的及びその価額 | 各社員が何(金銭または現物)をいくら出資するのかを記載します。金銭出資の場合はその金額、現物出資の場合はその目的物と価額を記載します。 |
相対的記載事項には、業務執行社員や代表社員の定め、利益の配当に関する定めなどがあります。
任意的記載事項には、事業年度や役員の任期(合同会社では任意)など、法律の範囲内で自由に定められる事項が含まれます。
合同会社の定款は認証不要
株式会社の場合、作成した定款は公証役場で公証人の認証を受ける必要がありますが、合同会社の場合は定款の認証手続きは不要です。
これにより、認証手数料(約5万円)がかからず、手続きの手間も省けます。
収入印紙代を節約するなら電子定款
紙の定款を作成した場合、収入印紙代として4万円が必要になります。
しかし、PDF形式で作成する「電子定款」であれば、この収入印紙代が不要となり、設立費用を節約できます。
電子定款を作成するには、ICカードリーダーライタやマイナンバーカード、専用のソフト(Adobe Acrobatなど)が必要です。
自分で環境を整えるのが難しい場合は、行政書士などの専門家や、電子定款作成に対応した会社設立支援サービスを利用することも検討しましょう。
ステップ2 資本金を払い込む
定款の作成が終わったら、次に出資者(社員)が定款で定めた資本金を払い込む手続きを行います。
会社設立登記の際に、資本金が適切に払い込まれたことを証明する書類が必要になります。
代表社員個人の口座へ振り込む
会社設立前はまだ法人口座を開設できないため、発起人(通常は代表社員となる人)の個人名義の銀行口座に、各社員が自身の出資額を振り込みます。
新しく口座を開設する必要はなく、既存の口座を利用できますが、他の取引と混同しないよう、入金記録が明確に残るように注意しましょう。
通帳には振込人名と金額が記帳されるように振り込むのが確実です。
なお、現物出資(不動産、自動車、有価証券など)がある場合は、金銭出資とは別に手続きが必要です。
価額の調査など複雑な場合もあるため、事前に確認しておきましょう。
払込証明書を作成する
資本金の払い込みが完了したら、それが証明できる書類として「払込証明書」を作成します。
払込証明書には以下の内容を記載します。
- 払い込まれた総額
- 払い込みがあった日付
- 会社名(設立する合同会社の商号)
- 代表社員の氏名・住所
この払込証明書に、資本金の入金が確認できる通帳のコピー(表紙、裏表紙(銀行名・支店名・口座番号・名義人がわかるページ)、該当の入金記録があるページ)を合綴し、各ページの綴じ目に会社代表印(または代表社員個人の実印)で契印を押します。
ステップ3 登記書類を作成する
定款作成、資本金の払い込みが完了したら、法務局へ提出する設立登記申請に必要な書類一式を準備します。
書類に不備があると登記申請が受理されなかったり、補正が必要になったりするため、正確に作成しましょう。
主な必要書類は以下の通りです。
ケースによっては追加書類が必要になることもあります。
| 書類名 | 概要 | 備考 |
|---|---|---|
| 合同会社設立登記申請書 | 設立登記を申請するためのメインとなる書類。法務局のウェブサイトでテンプレートや記載例が入手できます。登録免許税分の収入印紙を貼付する台紙も必要です。 | A4サイズで作成。 |
| 定款 | ステップ1で作成した定款。紙の定款の場合は原本、電子定款の場合はCD-Rなどに保存したもの、またはオンライン申請時に添付します。 | 紙の場合は製本し、社員全員の実印で契印。 |
| 代表社員就任承諾書 | 定款で代表社員を定めている場合でも、別途就任を承諾したことを証明する書面が必要な場合があります。(定款に代表社員の氏名・住所が記載され、その者が定款に実印を押印している場合は省略可能なケースも) | 代表社員個人の実印を押印。 |
| 本店所在地及び資本金決定書 | 定款で本店所在地の具体的な地番まで定めていない場合や、資本金の額が確定していない場合に、社員全員の同意によって決定したことを証明する書類。 | 社員全員の実印を押印。 |
| 社員の印鑑証明書 | 出資者である社員全員分が必要です。 | 発行後3ヶ月以内のもの。 |
| 払込証明書 | ステップ2で作成した、資本金の払い込みを証明する書類。 | 通帳コピーと合綴し、契印を押したもの。 |
| 印鑑届書 | 設立する会社の実印(代表社員印)を法務局に登録するための書類。登記申請と同時に提出します。 | 法務局のウェブサイトで様式を入手可能。代表社員個人の実印も必要。 |
| (必要な場合)現物出資に関する書類 | 財産引継書、資本金の額の計上に関する証明書など。 | 現物出資がある場合のみ。 |
これらの書類は、法務局のウェブサイトで提供されているテンプレートや記載例を参考に作成するとスムーズです。
不明な点があれば、法務局の相談窓口を利用することもできます。
ステップ4 法務局へ設立登記を申請する
登記書類一式が準備できたら、いよいよ法務局へ設立登記の申請を行います。
登記申請日が会社の設立日となります。
管轄の法務局を調べる
登記申請は、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局に対して行います。
どこの法務局が管轄かは、法務局のウェブサイトで確認できます。間違った法務局に申請しても受理されないため、事前に必ず確認しましょう。
登記申請の方法(窓口・郵送・オンライン)
登記申請の方法は、主に以下の3つがあります。
- 窓口申請: 管轄の法務局の窓口に直接書類を持参する方法です。書類に不備があればその場で指摘を受けられる可能性がありますが、法務局の開庁時間内に行く必要があります。
- 郵送申請: 管轄の法務局宛に書類一式を郵送する方法です。書留郵便で送るのが一般的です。法務局に行く手間は省けますが、書類到着までに時間がかかり、不備があった場合のやり取りも郵送や電話になります。
- オンライン申請: 法務省の「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)」を利用してインターネット経由で申請する方法です。電子定款との相性が良く、自宅やオフィスから24時間申請可能(メンテナンス時間を除く)というメリットがあります。ただし、専用ソフトのインストールや電子署名の準備が必要です。
自分の状況や書類の準備状況に合わせて最適な方法を選びましょう。
登録免許税(最低6万円)を納付する
合同会社の設立登記には、登録免許税という税金を納付する必要があります。
税額は「資本金の額 × 0.7%」ですが、この計算結果が6万円に満たない場合は、一律で6万円となります。
納付方法は、窓口申請や郵送申請の場合は、税額分の収入印紙を購入し、登記申請書の所定の台紙に貼付して提出します。
オンライン申請の場合は、インターネットバンキングやATMを利用した電子納付が可能です。
登記申請後、書類に不備がなければ、通常1週間~10日程度で登記が完了します。
登記が完了すると、会社の登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書が取得できるようになります。
ステップ5 会社設立後の諸手続き
法務局での設立登記が完了したら、会社設立の手続きは終わりではありません。
事業を開始するために必要な諸手続きがいくつかあります。これらの手続きを怠ると、税制上の優遇措置を受けられなかったり、罰則が科されたりする可能性もあるため、速やかに行いましょう。
主な手続きは以下の通りです。提出期限が設けられているものも多いので注意が必要です。
| 提出先 | 主な提出書類 | 提出期限の目安 |
|---|---|---|
| 税務署 | 法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 など | 設立後2ヶ月以内(青色申告は設立後3ヶ月以内または最初の事業年度終了日のいずれか早い方) |
| 都道府県税事務所・市町村役場 | 法人設立届出書(地方税) | 設立後1ヶ月~2ヶ月以内(自治体により異なる) |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届、被保険者資格取得届 など(役員報酬が発生する場合や従業員を雇用する場合) | 事実発生から5日以内 |
| 労働基準監督署 | 労働保険関係成立届、適用事業報告 など(従業員を1人でも雇用する場合) | 雇用日の翌日から10日以内 |
| ハローワーク(公共職業安定所) | 雇用保険適用事業所設置届、雇用保険被保険者資格取得届 など(従業員を1人でも雇用する場合) | 雇用日の翌日から10日以内 |
| 銀行 | 法人口座開設申込書、登記事項証明書、印鑑証明書、代表者の本人確認書類 など | 登記完了後、随時 |
特に税務署への法人設立届出書や青色申告の承認申請書は、提出期限が比較的短いため、登記完了後すぐに準備を始めましょう。
青色申告の承認を受けることで、欠損金の繰越控除など税制上のメリットがあります。
また、事業運営に不可欠な法人口座の開設も早めに行いましょう。
法人口座の開設には審査があり、時間がかかる場合もあります。
登記事項証明書(登記簿謄本)や印鑑証明書などが必要になるため、登記完了後に取得して申し込みます。
これらの手続きを一つずつ着実に進めることで、スムーズに事業を開始することができます。
合同会社設立の費用を自分で安く抑える方法

合同会社の設立手続きを自分で行う最大のメリットの一つは、専門家への依頼費用を節約できる点ですが、さらに工夫次第で設立にかかる実費も抑えることが可能です。
ここでは、合同会社設立の費用を自分でさらに安く抑えるための具体的な方法を詳しく解説します。
電子定款を活用して印紙代4万円を節約
合同会社設立における費用のうち、大きな割合を占めるのが定款に貼付する収入印紙代4万円です。
しかし、この費用は「電子定款」を作成することで完全に0円にすることが可能です。
これは、印紙税法上、課税対象となるのが「紙の文書」であり、電子データである電子定款は課税対象外となるためです。
電子定款とは、紙ではなくPDF形式などの電子データで作成された定款のことです。
この電子定款を作成し、法務省のオンラインシステムを通じて提出することで、印紙代が不要になります。
自分で電子定款を作成するためには、以下の準備が必要です。
- マイナンバーカード(または他の利用可能な電子証明書)
- ICカードリーダーライタ(マイナンバーカードを読み取るため)
- Adobe AcrobatなどのPDF作成ソフト
- 法務省提供のPDF署名プラグインソフト(無料でダウンロード可能)
- インターネット環境とパソコン
具体的な手順としては、まずWordなどで作成した定款の内容をPDFファイルに変換します。
その後、専用のソフト(署名プラグイン)を使って、そのPDFファイルに発起人(合同会社の場合は社員)全員分の電子署名を行います。
この電子署名が、紙の定款における押印の代わりとなります。
ただし、自分で電子定款を作成するには、ICカードリーダーライタやPDFソフトの購入費用がかかる場合がある点や、パソコンの設定やソフトの操作に慣れが必要というデメリットもあります。
もし、これらの準備や操作が難しいと感じる場合は、後述するように電子定款の作成のみを専門家(行政書士など)に依頼することも検討できます。
以下の表は、紙の定款と電子定款の主な違いをまとめたものです。
| 項目 | 紙定款 | 電子定款 |
|---|---|---|
| 定款認証(合同会社の場合) | 不要 | 不要 |
| 収入印紙代 | 40,000円 | 0円 |
| 作成に必要な主なもの | 紙、プリンター、印鑑など | パソコン、PDFソフト、マイナンバーカード、ICカードリーダーライタなど |
| メリット | 特別な機器やソフトが不要 | 印紙代が不要、データの保管・共有が容易 |
| デメリット | 印紙代が高い | 初期費用(機器・ソフト代)や設定の手間がかかる場合がある |
このように、電子定款を活用することは、合同会社設立費用を抑える上で非常に効果的な方法です。
オンライン登記申請システムを利用する
法務局への設立登記申請は、窓口持参や郵送だけでなく、オンラインで行うことも可能です。
法務省が提供する「登記・供託オンライン申請システム(登記ねっと)」を利用すれば、自宅やオフィスから登記申請手続きを進めることができます。
オンライン申請の主なメリットは以下の通りです。
- 法務局へ出向く時間と交通費を節約できる
- 24時間いつでも申請が可能(メンテナンス時間を除く)
- 登録免許税の納付もインターネットバンキング等で電子納付できる
- 申請状況をオンラインで確認できる
オンライン登記申請を行うためには、以下の準備が必要です。
- インターネット環境とパソコン
- 申請用総合ソフトのインストール(法務省ウェブサイトから無料でダウンロード可能)
- 申請者の電子証明書(マイナンバーカード等)
- ICカードリーダーライタ
電子定款とオンライン登記申請を組み合わせることで、定款作成から登記申請までの一連の手続きを完全にオンラインで完結させることも可能です。
これにより、設立手続きにかかる時間と手間を大幅に削減できます。
ただし、オンライン申請システムや申請用総合ソフトの操作には、ある程度の慣れが必要です。
マニュアルをよく読んだり、事前にテスト送信機能などを利用したりして、操作方法を確認しておくと良いでしょう。
また、電子証明書の取得や設定にも時間がかかる場合があるため、早めに準備を始めることが重要です。
なお、株式会社の設立においてはオンライン申請で登録免許税が減額される措置がありますが、合同会社設立の登録免許税(最低6万円)については、現在のところオンライン申請による減額措置はありません。
しかし、時間や交通費の節約、手続きの効率化というメリットは依然として大きいため、積極的に活用を検討する価値はあります。
必要最低限の書類作成のみ専門家に依頼する
「全て自分でやるのは不安だけれど、費用はできるだけ抑えたい」という場合には、設立手続きの一部だけを専門家(司法書士や行政書士)に依頼するという方法も有効です。
例えば、以下のような依頼方法が考えられます。
- 電子定款の作成・認証代行のみ依頼する: 上記で説明した電子定款の作成は、専用の機器やソフトが必要なため、ここだけを専門家に依頼する方法です。印紙代4万円は節約しつつ、自分で機器を揃える手間や費用を省けます。行政書士などに依頼する場合、数万円程度の費用がかかりますが、印紙代よりは安く済むケースが多いです。
- 定款作成のみ依頼する: 会社のルールブックとなる定款は、事業内容や将来の展開に合わせて適切な内容を盛り込むことが重要です。専門家に相談しながら作成することで、法的に有効で、かつ自社に適した定款を作成できます。
- 登記申請書類の作成・チェックのみ依頼する: 登記申請書類は種類が多く、記載内容も複雑です。自分で作成した書類に不備がないか専門家にチェックしてもらったり、作成自体を依頼したりすることで、申請の遅延や却下のリスクを減らすことができます。司法書士が登記申請代理の専門家となります。
- 設立に関する相談のみ行う: 手続き自体は自分で行う前提で、不明点や注意点について専門家からアドバイスをもらう方法です。時間単位などで相談料を設定している事務所もあります。
このように、自分の知識レベルやかけられる時間、予算に合わせて、専門家のサポートを部分的に活用することで、費用を抑えながらも、手続きの正確性や安心感を高めることができます。
どこまでを自分で行い、どこからを専門家に依頼するかを事前に検討し、複数の専門家に見積もりを取って比較検討することをおすすめします。
自分で合同会社を設立するときの注意点

合同会社の設立手続きは、株式会社に比べてシンプルで費用も抑えられますが、専門家に依頼せず自分で行う場合には、いくつか注意すべき点があります。
事前にこれらの注意点を理解し、対策を講じておくことで、スムーズな会社設立と、その後の安定した事業運営につながります。
書類の不備による登記申請の遅延リスク
自分で合同会社設立の登記申請を行う際に最も注意したいのが、提出書類の不備です。
法務局での登記審査は厳格に行われるため、わずかなミスでも補正(修正)を求められ、手続きが遅延する原因となります。
具体的には、以下のような不備が考えられます。
- 定款や登記申請書などの書類への誤字・脱字
- 必要書類の添付漏れ
- 押印すべき箇所への押し忘れ、または使用する印鑑の間違い(個人の実印と会社の実印など)
- 定款と登記申請書の記載内容の不一致(商号、本店所在地、事業目的など)
- 印鑑証明書の有効期限切れ(通常、発行から3ヶ月以内)
- 資本金の払込証明書の記載誤りや添付書類の不足
書類に不備があると、法務局から電話や書面で補正指示があります。
指示に従って書類を修正し、再提出する必要がありますが、修正内容によっては再度関係者の印鑑が必要になったり、書類を取り直したりする必要が生じ、大幅な時間のロスにつながる可能性があります。
特に、事業開始日が決まっている場合や、融資の申し込みを急いでいる場合には、登記の遅れが致命的になることも考えられます。
対策としては、書類作成後に複数回、複数人でチェックする体制を整えることが重要です。
また、法務局によっては事前相談窓口を設けている場合があるので、不安な点があれば積極的に活用しましょう。
時間に余裕を持ったスケジュールで進めることも、予期せぬ遅延リスクに備える上で大切です。
事業に必要な許認可の確認漏れ
合同会社の設立登記自体は、特定の事業目的を記載すれば完了しますが、実際にその事業を開始するためには、業種によって行政庁からの許認可が必要となる場合があります。
この許認可の確認を怠り、無許可で事業を開始してしまうと、罰金や営業停止命令などの厳しい行政処分を受けるリスクがあります。
許認可が必要となる主な業種の例としては、以下のようなものがあります。
| 業種例 | 主な許認可 | 主な管轄行政庁(例) |
|---|---|---|
| 飲食店、喫茶店 | 飲食店営業許可 | 保健所 |
| 建設業 | 建設業許可 | 国土交通省(地方整備局)、都道府県 |
| 中古品の売買(リサイクルショップ、古着屋など) | 古物商許可 | 都道府県公安委員会(窓口は警察署) |
| 人材派遣業 | 労働者派遣事業許可 | 厚生労働省(労働局) |
| 運送業(トラック、タクシーなど) | 一般貨物自動車運送事業許可、一般乗用旅客自動車運送事業許可など | 国土交通省(運輸局) |
| 不動産業(宅地建物の売買・仲介など) | 宅地建物取引業免許 | 国土交通省、都道府県 |
| 旅行業 | 旅行業登録 | 観光庁、都道府県 |
| 酒類の販売業 | 酒類販売業免許 | 税務署 |
上記はあくまで一例であり、これ以外にも多くの業種で許認可が必要です。
許認可の種類によって、申請先、必要書類、審査基準、取得までにかかる期間は大きく異なります。
また、定款の事業目的に特定の文言が含まれていないと許認可が下りないケースや、会社設立後でないと申請できない許認可もあります。
自分で設立手続きを行う際は、ご自身の事業が許認可を必要とするかどうか、必ず事前に確認しましょう。
確認方法としては、関係省庁のウェブサイトを調べる、管轄の行政庁に問い合わせる、または行政書士などの専門家に相談するといった方法があります。
許認可の取得漏れは事業継続に関わる重大な問題ですので、設立準備段階で確実にチェックしてください。
設立後の税務や社会保険手続きの失念
法務局への設立登記申請が完了し、会社が設立された後にも、税務署や年金事務所など、各行政機関への届出が義務付けられています。
これらの手続きを忘れてしまうと、税制上の優遇措置が受けられなくなったり、追徴課税や延滞税、社会保険料の遡及支払いなど、思わぬペナルティが発生したりする可能性があります。
設立後に必要となる主な手続きは以下の通りです。
提出期限が短いものもあるため、登記完了後、速やかに行動しましょう。
| 提出先 | 主な届出書類 | 提出期限(目安) |
|---|---|---|
| 税務署 | 法人設立届出書 | 設立日から2ヶ月以内 |
| 税務署 | 青色申告の承認申請書 | 設立日から3ヶ月を経過した日、または最初の事業年度終了日のいずれか早い日の前日まで |
| 税務署 | 給与支払事務所等の開設届出書 | 給与支払事務所設置から1ヶ月以内 |
| 税務署 | 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 適用を受けたい月の前月末まで |
| 都道府県税事務所・市町村役場 | 法人設立届出書(地方税) | 各自治体の条例による(通常、設立日から1ヶ月~2ヶ月以内) |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 新規適用届 | 適用事業所となった日から5日以内 |
| 年金事務所 | 健康保険・厚生年金保険 被保険者資格取得届 | 資格取得日から5日以内 |
| 労働基準監督署(従業員雇用時) | 労働保険関係成立届 | 保険関係成立日から10日以内 |
| 労働基準監督署(従業員雇用時) | 労働保険概算保険料申告書 | 保険関係成立日から50日以内 |
| ハローワーク(従業員雇用時) | 雇用保険適用事業所設置届 | 設置日の翌日から10日以内 |
| ハローワーク(従業員雇用時) | 雇用保険被保険者資格取得届 | 資格取得日の属する月の翌月10日まで |
特に注意が必要なのは社会保険(健康保険・厚生年金保険)です。
合同会社は、たとえ社長一人(代表社員のみ)であっても、法人から役員報酬を受け取る場合は原則として社会保険への加入が義務付けられています。
加入手続きを怠ると、後から最大2年分の保険料を遡って請求される可能性があります。
これらの設立後の手続きは多岐にわたり、それぞれ提出先や期限が異なります。
設立前に必要な手続きをリストアップし、スケジュールを立てておくことが重要です。
不安な場合は、税理士や社会保険労務士に相談することも検討しましょう。
定款の内容は将来を見据えて慎重に決める
定款は、会社の組織や運営に関する基本的なルールを定めたものであり、「会社の憲法」とも呼ばれる非常に重要な書類です。
合同会社の定款は株式会社と異なり、公証人による認証が不要なため、比較的自由に作成できますが、安易にインターネット上のテンプレートをそのまま利用するのは避けるべきです。
定款の内容は、設立後の会社運営や将来の事業展開、社員間の関係性に大きな影響を与えます。
後から変更することも可能ですが、その都度、社員全員の同意や法務局での変更登記(登録免許税が必要な場合あり)が必要となり、手間とコストがかかります。
そのため、設立時点で自社の実情や将来の計画を十分に考慮し、慎重に内容を決定する必要があります。
特に以下の項目については、注意深く検討しましょう。
事業目的の記載方法
定款には、会社が行う事業内容を「目的」として記載します。
この事業目的は、具体的かつ明確に記載する必要があります。
漠然とした表現や、許認可が必要な事業において要件を満たさない記載では、登記申請が受理されなかったり、後の許認可申請に支障が出たりする可能性があります。
また、将来的に行う可能性のある事業も、あらかじめ定款に記載しておくことをお勧めします。
これにより、新規事業を開始する際に定款変更の手続き(登録免許税3万円)を省略できます。
ただし、あまりにも多くの事業目的を羅列すると、金融機関や取引先から「何の会社か分かりにくい」という印象を与えかねないため、関連性の高い事業に絞るなど、バランスを考慮しましょう。
許認可が必要な事業を行う場合は、その許認可の要件を満たす適切な文言で事業目的を記載することが不可欠です。
事前に管轄の行政庁や専門家に確認しておくと安心です。
社員(出資者)構成と利益配分
合同会社では、出資者のことを「社員」と呼びます。
株式会社と異なり、原則として出資額の大小にかかわらず、社員一人につき一個の議決権が与えられます。
また、利益の配分についても、出資比率に比例させる必要はなく、定款で自由に定めることが可能です。
この自由度の高さはメリットである一方、社員間で意見が対立した場合や、貢献度に応じた利益配分を望む場合に、トラブルの原因となる可能性も秘めています。
例えば、出資額が少なくても経営への関与度が高い社員がいる場合や、特定の業務を担当する社員にインセンティブを与えたい場合など、実情に合わせて議決権の割合や利益配分のルールを定款で明確に定めておくことが、円滑な会社運営のために重要です。
また、社員の加入や退社、持分の譲渡に関するルールも定款で定めておくことで、将来的なメンバー構成の変化にもスムーズに対応できます。
本店所在地の記載方法
定款には、会社の本店所在地を記載する必要があります。
記載方法としては、最小行政区画(例:「東京都千代田区」)まで記載する方法と、地番まで含めて詳細に記載する方法(例:「東京都千代田区丸の内一丁目1番1号」)があります。
登記申請においては、地番まで含めた正確な所在地が必要ですが、定款への記載は最小行政区画まででも問題ありません。
地番まで定款に記載してしまうと、将来、同じ市区町村内で本店を移転する場合でも、定款変更の手続きと変更登記(登録免許税3万円)が必要になってしまいます。
設立当初は自宅を本店所在地とする場合や、将来的に事業拡大に伴う移転の可能性がある場合は、定款には最小行政区画までの記載に留めておく方が、移転時の手続きやコストの面で有利になることがあります。
ただし、定款に最小行政区画までしか記載しない場合は、別途、社員の決定書などで具体的な所在地を定める必要があります。
公告方法の選択
会社法では、会社が重要な事項(例:計算書類の開示、合併、解散など)を知らせるための公告方法を定款で定めることとされています。
選択肢としては、「官報に掲載する方法」「時事に関する事項を掲載する日刊新聞紙に掲載する方法」「電子公告(自社のウェブサイトなど)」のいずれか、またはこれらを組み合わせた方法があります。
定款で公告方法を定めなかった場合は、自動的に「官報に掲載する方法」となります。
官報公告は最も確実な方法ですが、掲載費用が比較的高額(数万円~)です。日刊新聞紙への掲載はさらに高額になる傾向があります。
一方、電子公告は、自社のウェブサイトに掲載することで費用を抑えられるメリットがあります。
ただし、決算公告を電子公告で行う場合は、貸借対照表を5年間継続して掲載する必要があり、ウェブサイトの維持管理の手間がかかります。
また、公告期間中にサーバーダウンなどで閲覧できない期間が生じないよう注意が必要です。
必要に応じて、公告内容を調査する機関(調査機関)に依頼することもできますが、その場合は別途費用が発生します。
会社の規模や情報発信体制、コストなどを考慮し、自社に最も適した公告方法を選択し、定款に明記しましょう。
まとめ
合同会社の設立は、専門家に依頼せず自分で行うことが可能です。
最大のメリットは設立費用を抑えられる点ですが、時間や手間がかかり、書類作成ミスなどのリスクも伴います。
費用削減には電子定款の活用が有効で、収入印紙代4万円を節約できます。
ただし、書類不備による登記遅延や設立後の手続き漏れには十分注意が必要です。
この記事で解説した手順や注意点を参考に、ご自身での設立を検討してみてください。
不安な点があれば、専門家への相談も有効な選択肢となります。









