「いきなり法人化」は、売上が一定額を超える見込みなら税金や社会的信用の面で非常にお得です。
しかし、安易に決めると後悔することも。
この記事では、税理士がメリット・デメリットを比較し、あなたが法人化すべきかの判断基準を具体的に解説。
会社設立の手続きから注意点まで、後悔しないための全知識を網羅しました。最適なスタートを切るために、ぜひご一読ください。
「いきなり法人化」とは?個人事業主から始める場合との違い
事業を始めようと考えたとき、多くの人がまず「個人事業主」としてスタートし、事業が軌道に乗ってきた段階で「法人成り」を検討する、という流れを想像するかもしれません。
しかし、近年では事業を開始するタイミングで、最初から法人を設立する「いきなり法人化」という選択肢が注目を集めています。
これは、フリーランスやスタートアップといった多様な働き方が広がる中で、事業の成長を加速させるための戦略として選ばれるケースが増えているためです。
この章では、まず「いきなり法人化」が具体的にどういうものなのかを解説し、従来一般的であった個人事業主からスタートする場合と何が決定的に違うのかを、明確に比較しながら掘り下げていきます。
ご自身の事業計画に最適な選択をするための、最初のステップとなる知識を身につけましょう。
事業開始と同時に会社を設立すること
「いきなり法人化」とは、その名の通り、個人事業主としての期間を経ずに、事業を開始するのと同時に株式会社や合同会社といった法人を設立することを指します。
税務署に「開業届」を提出するだけで始められる個人事業主とは異なり、法務局への登記申請など、法的に定められた手続きを経て「会社」という人格を創り出すことからスタートします。
これまでは、まず個人で事業を始めてみて、売上が安定し、所得が一定額を超えたタイミングで節税などを目的に法人化する「法人成り」が一般的なルートでした。
しかし、初めから大きな資金調達を計画していたり、大手企業との取引を視野に入れていたり、あるいは社会的な信用を早期に獲得したいといった明確な目的がある場合には、「いきなり法人化」が非常に有効な戦略となり得るのです。
個人事業主と法人の決定的な違い
では、個人事業主と法人では、具体的にどのような違いがあるのでしょうか。
両者は事業を行う主体という点では同じですが、法律上の位置づけ、責任の範囲、税金、社会的信用など、多くの面で根本的な違いがあります。
ここでは、その決定的な違いを表で比較し、それぞれの特徴を詳しく見ていきましょう。
| 項目 | 個人事業主 | 法人(株式会社など) |
|---|---|---|
| 設立手続き | 税務署に開業届を提出するだけで、比較的簡単。費用もかからない。 | 定款の作成・認証、法務局への登記申請が必要。手間と費用(登録免許税など約20万円〜)がかかる。 |
| 事業の主体 | 事業主個人 | 法律によって人格を与えられた「法人」 |
| 責任の範囲 | 無限責任 事業上の負債は、個人の全財産で返済する義務を負う。 | 有限責任 出資者は、原則として自分が出資した金額の範囲内でのみ責任を負う。 |
| 税金 | 個人の所得に対して「所得税」が課される。税率は所得に応じて高くなる累進課税(5%〜45%)。 | 法人の所得に対して「法人税」が課される。税率はほぼ一定(約23%)。その他に法人住民税、法人事業税などがある。 |
| 会計・経理 | 比較的簡易な会計処理も可能(青色申告・白色申告)。 | 複式簿記による厳密な会計処理が義務付けられ、決算書の作成・公開が必要。 |
| 社会的信用 | 個人の信用力に依存する。 | 登記情報が公開されており、一般的に個人事業主よりも高い信用を得やすい。 |
| 廃業手続き | 税務署に廃業届を提出するだけで、比較的簡単。 | 解散登記や清算手続きが必要で、時間と費用がかかる。 |
この表で特に重要なのが「責任の範囲」です。
個人事業主は、事業で失敗して多額の借金を抱えた場合、事業用の資金だけでなく、個人の預貯金や自宅といったプライベートな財産も返済に充てなければなりません。
これを「無限責任」といいます。
一方、法人の場合は「有限責任」が原則です。
会社の借金はあくまで会社のものであり、社長(代表取締役)や株主といった出資者は、自分が出資した範囲でしか責任を負いません。
ただし、社長個人が会社の融資の連帯保証人になっている場合は、個人も返済義務を負うため注意が必要です。
このように、個人事業主と法人には明確な違いが存在します。
「いきなり法人化」を検討するということは、事業開始時点から法人の持つ「社会的信用」や「有限責任」といったメリットを享受する道を選ぶことを意味します。
次の章からは、この選択がもたらす具体的なメリットや、逆に知っておかなければならないデメリットについて、さらに詳しく解説していきます。
税理士が厳選 いきなり法人化のメリット5選

事業を始める際、多くの人がまず個人事業主としてスタートすることを考えます。
しかし、事業計画や将来の展望によっては、最初から法人を設立する「いきなり法人化」が非常に有効な選択肢となります。
ここでは、税務のプロである税理士が、いきなり法人化がもたらす5つの大きなメリットを徹底的に解説します。
メリット1 税金の負担を軽減できる可能性がある
いきなり法人化を検討する最大の動機は「節税」でしょう。
個人事業主と法人では税金の計算方法が根本的に異なり、一定以上の利益が見込める場合、法人の方が手元に残るお金を最大化できる可能性があります。
法人税と所得税の税率差による節税
個人事業主の所得にかかる「所得税」は、所得が増えれば増えるほど税率が高くなる「超過累進課税」が採用されています。
所得税と住民税を合わせると、最大で55%もの税率が課せられます。
一方、法人の利益にかかる「法人税」は、資本金1億円以下の普通法人の場合、所得が800万円以下の部分とそれを超える部分で税率が変わるものの、基本的には比例税率です。
所得税のように所得の増加に伴って税率が青天井に上がることはありません。
以下の表で、所得税と法人実効税率(法人税、地方法人税、法人住民税、事業税の合計)の構造の違いを確認してみましょう。
| 課税される所得金額 | 所得税の税率(住民税約10%含まず) | 法人実効税率の目安(中小企業) |
|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 約25%(所得800万円以下の部分) |
| 195万円超 330万円以下 | 10% | |
| 330万円超 695万円以下 | 20% | |
| 695万円超 900万円以下 | 23% | 約34%(所得800万円超の部分) |
| 900万円超 1,800万円以下 | 33% | |
| 1,800万円超 4,000万円以下 | 40% | |
| 4,000万円超 | 45% |
この税率構造の違いにより、一般的に課税所得が800万円から900万円を超えるあたりから、法人の方が税負担上有利になると言われています。
事業開始時から高い売上と利益が見込める場合は、いきなり法人化することで大きな節税効果が期待できます。
経費として認められる範囲が広がる
法人化すると、個人事業主では経費にできなかった支出も、法人の経費(損金)として計上できる場合があります。
これにより会社の利益を圧縮し、結果的に法人税の節税につながります。
- 役員社宅制度の活用:法人が契約した物件を役員に貸し出すことで、家賃の一部を法人の経費にできます。個人が支払う家賃負担を軽減しつつ、会社の利益を圧縮できる有効な手段です。
- 出張手当(日当)の支給:出張時の交通費や宿泊費といった実費とは別に、出張手当を非課税で支給できます。受け取った役員や従業員は所得税がかからず、支払った法人は経費として計上できます。
- 生命保険料の損金算入:法人契約の生命保険の中には、保険料の全額または一部を経費にできる商品があります。役員の万が一の保障や退職金の準備をしながら、税負担を軽減できます。
- 役員退職金の支給:役員への退職金は、経費として計上できるだけでなく、受け取る側も税制上非常に優遇されています。個人事業主にはない、大きな節税メリットです。
これらの制度をうまく活用することで、可処分所得を実質的に増やしながら、効果的な節税を実現できるのが法人化の魅力です。
家族への役員報酬で所得を分散できる
個人事業主が家族に給与を支払う場合、「青色事業専従者給与」という制度を利用しますが、事前に届出が必要で、その事業に専ら従事している必要があるなど、いくつかの制約があります。
一方、法人では、事業を手伝う家族を役員にし、業務内容や貢献度に応じた役員報酬を支払うことができます。
これにより、社長一人に集中しがちな所得を家族に分散させることが可能です。
所得税は累進課税のため、所得を分散させることで一人ひとりの税率が下がり、世帯全体で見たときの手取り額を増やす効果が期待できます。
また、給与を受け取る家族それぞれが給与所得控除を使える点も大きなメリットです。
メリット2 社会的な信用力が高まる
法人格を持つことは、税金面だけでなく、ビジネスを行う上での「信用力」を大きく向上させます。
これは、資金調達や取引先の拡大において非常に重要な要素となります。
金融機関からの融資を受けやすくなる
金融機関が融資審査を行う際、個人事業主よりも法人の方が高く評価される傾向にあります。
法人は法律に基づいて設立され、会計処理も厳格に行われるため、事業と個人の資産が明確に分離されており、決算書の信頼性が高いと判断されるからです。
日本政策金融公庫などの公的な融資制度においても、法人の方が融資の選択肢や上限額で有利になる場合があります。
事業の成長に不可欠な資金調達を円滑に進める上で、法人格は強力な後ろ盾となります。
大手企業との取引で有利になる
大企業や一部の業界では、コンプライアンスや与信管理の観点から「取引先は法人のみ」という内規を設けているケースが少なくありません。
個人事業主というだけで、取引のスタートラインに立てない可能性があるのです。
法人登記されていることで、事業の実在性や継続性が公的に証明され、取引先からの信頼を得やすくなります。
これにより、個人事業主では難しかった大手企業との契約や、新たなビジネスチャンスを掴む可能性が広がります。
メリット3 決算月を自由に決められる
個人事業主の事業年度は、法律により1月1日から12月31日までと定められており、確定申告は翌年の2月16日から3月15日に行います。
これは変更することができません。
しかし、法人の場合は、定款で事業年度を自由に設定することができます。
例えば、会社の繁忙期を避け、比較的落ち着いている時期に決算期を設定すれば、余裕を持って決算作業や納税準備を進めることができます。
また、消費税の免税事業者としての期間を最大限活用するなど、戦略的に決算月を決めることも可能です。
この柔軟性は、効率的な事業運営に大きく貢献します。
メリット4 事業承継やM&Aがスムーズに進む
将来的に事業を子どもに引き継がせたい、あるいは会社を売却したいと考えている場合、法人化は極めて有効です。
個人事業の場合、事業主が亡くなると事業用の資産はすべて相続財産となり、事業の継続が困難になることがあります。
法人の場合、事業そのものは会社という人格が所有しているため、経営者が変わっても事業は継続されます。
事業承継は株式を相続または贈与することで完了し、手続きが非常にスムーズです。
また、M&A(企業の合併・買収)においても、個人事業の売買に比べて株式譲渡という明確な手法があるため、買い手が見つかりやすく、より良い条件での売却が期待できます。
メリット5 採用活動で人材を確保しやすくなる
事業の成長には優秀な人材の確保が不可欠です。
求職者の視点に立つと、「個人商店」よりも「株式会社」といった法人格を持つ会社の方が、安定性や将来性を感じ、安心して応募できる傾向があります。
また、法人は社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられています。
これは従業員にとって大きな安心材料であり、福利厚生の充実度を示す重要な指標です。
社会的な信用の高さと充実した福利厚生は、採用活動において大きなアピールポイントとなり、優秀な人材の獲得競争で有利に働きます。
知らないと損する いきなり法人化のデメリットと注意点
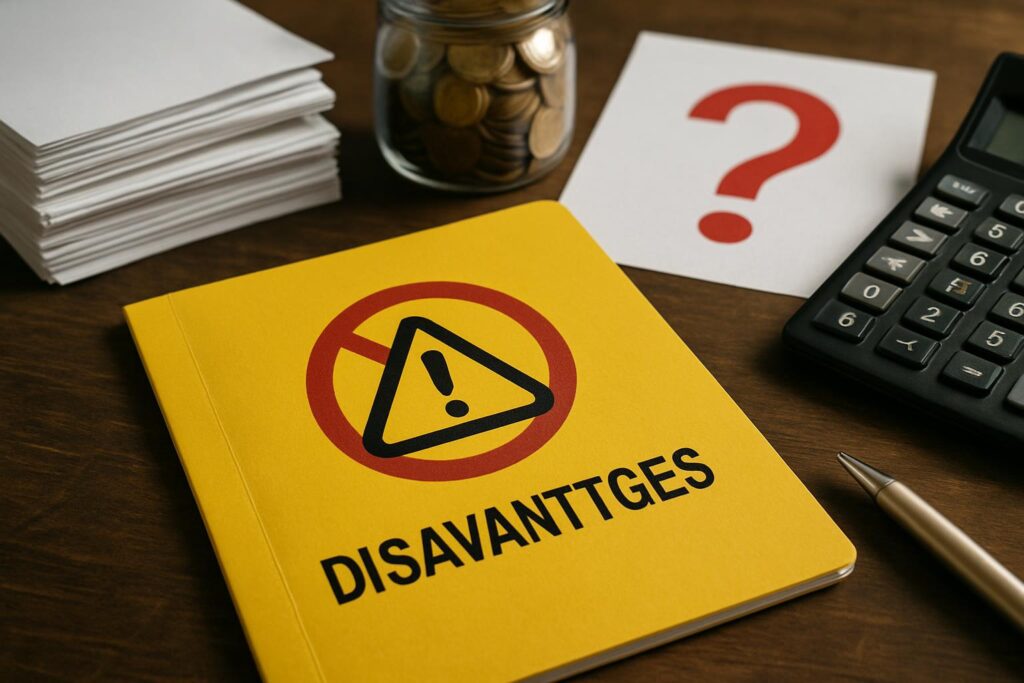
「いきなり法人化」には税制面や信用力向上といった華やかなメリットがある一方で、見過ごすことのできないデメリットや注意点も存在します。
メリットだけに目を奪われて安易に法人化を進めてしまうと、「こんなはずではなかった」と後悔するケースも少なくありません。
ここでは、事業を始める前に必ず知っておくべき法人化の現実的な負担やリスクについて、具体的に解説します。
会社設立に費用と手間がかかる
個人事業主が税務署に「開業届」を一枚提出するだけで事業を始められるのに対し、法人の設立には時間的・金銭的なコストが格段に多くかかります。
まず、設立手続き自体が複雑で、多くの書類作成や申請が必要です。
そして、その過程で必ず発生するのが「法定費用」です。
設立する会社形態によって費用は異なりますが、主な法定費用は以下の通りです。
| 費用項目 | 株式会社 | 合同会社 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 定款に貼る収入印紙代 | 40,000円 | 40,000円 | 電子定款の場合は不要 |
| 定款の認証手数料 | 30,000円~50,000円 | 不要 | 資本金の額によって変動 |
| 登録免許税 | 最低150,000円 | 最低60,000円 | 資本金の0.7%(最低額に満たない場合は最低額を納付) |
| 合計(目安) | 約220,000円~ | 約100,000円~ | 電子定款を利用した場合、印紙代4万円が節約できます |
この他にも、会社の代表印(実印)の作成費用や、手続きを司法書士などの専門家に依頼する場合は別途報酬が発生します。
個人事業主の開業がほぼ無料でできることを考えると、これは非常に大きな初期投資と言えるでしょう。
事業開始前から数十万円の支出があることを覚悟しておく必要があります。
赤字でも法人住民税の支払い義務がある
個人事業主の場合、事業が赤字であれば所得税や住民税はかかりません。
しかし、法人の場合はたとえ事業が赤字であっても、最低限支払わなければならない税金があります。
それが「法人住民税の均等割」です。
法人住民税は、利益に応じて課税される「法人税割」と、会社の規模(資本金や従業員数)に応じて定額で課税される「均等割」の2つで構成されています。
このうち「均等割」は、会社の存在そのものに対して課される税金であるため、利益が出ているかどうかに関わらず納税義務が生じます。
金額は自治体によって異なりますが、資本金1,000万円以下、従業員50人以下の最も小規模な会社であっても、最低で年間約7万円の支払いが必要です。
売上が全く立っていない創業初年度から、この負担は重くのしかかります。
利益が出ていないのに税金を払い続けなければならないという事実は、法人化する上で必ず理解しておくべき重要なポイントです。
社会保険への加入が必須となり負担が増える
法人化による最も大きなコスト増の一つが、社会保険料の負担です。法人を設立すると、たとえ社長一人だけの会社であっても、健康保険と厚生年金保険への加入が法律で義務付けられています。
個人事業主であれば国民健康保険と国民年金に加入しますが、法人の役員になると、役員報酬額に応じた社会保険料を支払うことになります。
この保険料は、会社と個人が半分ずつ負担する「労使折半」という仕組みになっています。
例えば、役員報酬を月額30万円に設定した場合、社会保険料の総額は約9万円となり、そのうちの半額である約4.5万円を会社が負担しなければなりません。
これは給与とは別に発生する固定費であり、会社の資金繰りを大きく圧迫する要因となります。
将来的に従業員を雇用すれば、その従業員の分の社会保険料も会社が半額負担することになり、負担はさらに増大します。
この継続的なランニングコストの発生は、法人化を検討する際に最も慎重にシミュレーションすべき点です。
経理や税務申告などの事務作業が複雑になる
個人事業主の確定申告と比べて、法人の経理処理や税務申告は格段に複雑化し、専門的な知識が求められます。
まず、日々の経理処理においては、個人事業主の簡易的な帳簿付けとは異なり、正規の簿記の原則に従った「複式簿記」での記帳が必須となります。
貸借対照表や損益計算書といった財務諸表を作成する必要があり、会計に関する知識がなければ対応は困難です。
さらに、年に一度の税務申告では、「法人税申告書」を作成します。
この申告書は、所得税の確定申告書とは比較にならないほど複雑で、様々な調整項目を記載した「別表」と呼ばれる十数種類の書類を添付する必要があります。
税法に関する深い理解がなければ、正確な申告書を自力で作成することは極めて難しいでしょう。
そのため、ほとんどの法人が会計ソフトを導入し、税理士と顧問契約を結んでいます。
税理士に依頼すれば正確な申告が可能になりますが、当然ながら顧問料や決算申告料といった費用が発生します。
これもまた、法人を維持していくための新たなランニングコストとなるのです。
あなたはどっち?いきなり法人化すべきかの判断基準

ここまで、いきなり法人化するメリットとデメリットを解説してきました。
しかし、「結局、自分の場合はどうすれば良いの?」と迷われている方も多いでしょう。
法人化は一度行うと簡単には戻せません。後悔しないために、ご自身の状況に合わせて最適な選択をするための3つの判断基準を具体的に解説します。
売上や所得の目安で判断する
法人化を検討する最も大きな動機の一つが「節税」です。個人事業主の所得税は、所得が増えるほど税率が高くなる「累進課税」であるのに対し、法人税は基本的に一定の税率です。
そのため、ある一定の所得を超えると、法人の方が税負担は軽くなる傾向にあります。
一般的に、その分岐点となるのは課税所得が800万円〜900万円と言われています。
これは、所得税率が法人税率を大きく上回るラインです。もちろん、これはあくまで目安であり、経費の額や家族構成、適用される控除によって変動します。
以下の表は、個人事業主と法人(役員報酬800万円と仮定)の税金・社会保険料の負担を大まかに比較したものです。
所得が増えるにつれて、法人の方が有利になる可能性があることがわかります。
| 課税所得 | 個人事業主の負担額(所得税・住民税・事業税・国保) | 法人の負担額(法人税等・役員個人の税・社会保険料) |
|---|---|---|
| 500万円 | 約180万円 | 約250万円 |
| 800万円 | 約320万円 | 約310万円 |
| 1,000万円 | 約430万円 | 約380万円 |
| 1,500万円 | 約700万円 | 約550万円 |
※上記はあくまで簡易的なシミュレーションです。個別の状況により金額は大きく異なります。
また、税金面でもう一つ重要なのが消費税です。原則として、課税売上高が1,000万円を超えた翌々年から消費税の納税義務が発生します。
しかし、個人事業主から法人成りした場合、資本金1,000万円未満などの要件を満たせば、設立から最大2年間は消費税の納税が免除される可能性があります。
売上が1,000万円を超えそうなタイミングは、法人化を検討する絶好の機会と言えるでしょう。(※インボイス制度の登録状況により取り扱いは異なります。)
事業内容や取引先で判断する
税金だけでなく、あなたの事業内容や主な取引先も重要な判断基準となります。
特に、以下のようなケースでは、売上規模に関わらず「いきなり法人化」を検討する価値があります。
BtoB(法人向け)事業がメインの場合
もしあなたのビジネスが、企業を相手にするBtoB事業であるなら、法人格は大きな意味を持ちます。
大手企業の中には、与信管理の観点から「法人でなければ取引しない」という内規を設けているケースが少なくありません。
個人事業主というだけで、大きなビジネスチャンスを逃してしまう可能性があるのです。
コンサルタント、Web制作、システム開発、卸売業など、法人との取引が中心となる事業を始める場合は、最初から法人設立を視野に入れるべきでしょう。
許認可が必要な事業の場合
建設業、飲食業、古物商、人材派遣業など、事業を行うために国や自治体からの許認可が必要な業種があります。
これらの許認可は、個人事業主よりも法人の方が取得しやすい、あるいは公共事業の入札などでは法人格が有利に働く場合があります。
事業に必要な許認可の要件を確認し、法人格が必要かどうかを事前にリサーチしておくことが重要です。
多額の資金調達や設備投資が必要な場合
事業開始にあたり、金融機関からの融資や多額の設備投資が必要な場合も、法人化が有利です。
一般的に、金融機関は個人事業主よりも法人に対しての方が融資に積極的です。
これは、法人が会計処理の透明性が高く、事業の継続性が担保されやすいと判断されるためです。
日本政策金融公庫の創業融資などでも、法人の方がより大きな金額を借り入れできる傾向があります。
将来の事業計画で判断する
目先の利益だけでなく、5年後、10年後を見据えた長期的な事業計画も、法人化を判断する上で欠かせない要素です。
事業拡大や従業員雇用の予定があるか
将来的に従業員を雇用し、事業を大きくしていきたいと考えているなら、法人化が適しています。
法人であれば、社会保険への加入が義務付けられますが、これは従業員にとって福利厚生が手厚いという安心感につながり、優秀な人材を確保しやすくなるという採用面でのメリットにもなります。
また、事業拡大に伴う責任の所在を明確にする上でも、法人格は有効です。
事業承継やM&A(売却)を視野に入れているか
個人事業は、事業主個人の資産と事業用資産の区別が曖昧で、事業主が亡くなると事業を引き継ぐのが困難になるケースがあります。
一方、法人であれば、株式の譲渡によってスムーズに事業承継やM&A(第三者への売却)を行うことができます。将来的に事業を子供に継がせたい、あるいは事業を売却して利益を得たい(バイアウト)という「出口戦略」を描いているのであれば、最初から法人としてスタートする方が圧倒的に有利です。
外部からの出資を受ける計画があるか
ベンチャーキャピタルやエンジェル投資家から出資を受けて、事業を急成長させたいと考えている場合、法人(特に株式会社)であることが絶対条件です。
出資とは、会社の株式を引き受けてもらうことであり、株式を発行できない個人事業主では、そもそも出資を受けるという選択肢が存在しません。
将来的な資金調達の可能性を少しでも考えているなら、いきなり法人化すべきと言えるでしょう。
後悔しないための「いきなり法人化」手続きの全知識

「いきなり法人化」を決意したら、次はいよいよ会社設立の手続きです。
手続きには時間と手間がかかりますが、一つひとつのステップを確実に進めることで、スムーズなスタートを切ることができます。
ここでは、会社形態の選択から設立後の届出まで、後悔しないために知っておくべき手続きの全知識を網羅的に解説します。
株式会社と合同会社どちらを選ぶべきか
法人にはいくつかの種類がありますが、新たに設立される会社のほとんどは「株式会社」か「合同会社」です。
それぞれに特徴があり、ご自身の事業計画や将来のビジョンに合わせて最適な形態を選ぶことが重要です。
まずは、両者の違いを比較してみましょう。
| 項目 | 株式会社 | 合同会社 |
|---|---|---|
| 設立費用(法定費用) | 約20万円~(定款印紙代4万円、認証手数料3~5万円、登録免許税15万円~) | 約6万円~(登録免許税6万円~)※定款印紙代・認証手数料は不要 |
| 社会的信用度 | 高い傾向にある | 株式会社に比べると低いと見られる場合がある |
| 出資者の名称 | 株主 | 社員 |
| 出資者の責任 | 有限責任(出資額の範囲内) | 有限責任(出資額の範囲内) |
| 意思決定 | 株主総会(所有と経営が分離) | 原則として社員全員の同意(所有と経営が一致) |
| 利益の配分 | 出資比率(株式数)に応じて配当 | 定款で自由に決められる |
| 役員の任期 | 原則2年(最長10年まで伸長可)。任期ごとに登記が必要。 | 任期なし。登記の変更は不要。 |
| 資金調達 | 株式発行による増資、社債発行など多様。上場(IPO)も可能。 | 出資者(社員)の追加が基本。外部からの大規模な資金調達には不向き。 |
株式会社が向いているケースは、将来的に上場(IPO)を目指したり、外部から広く資金調達を行ったりするなど、事業の大きな成長と拡大を視野に入れている場合です。
社会的信用度が高いため、大手企業との取引や金融機関からの融資においても有利に働くことがあります。
一方、合同会社が向いているケースは、設立コストを抑えてスピーディーに事業を始めたい場合や、経営の自由度を高く保ちたい場合です。
BtoCのビジネスや、特定のスキルを持つ少人数で事業を行う場合に適しています。
Appleの日本法人であるApple Japan合同会社のように、知名度の高い企業でも採用されている形態です。
会社設立に必要な手続きの6ステップ
会社設立の手続きは、大まかに6つのステップに分かれます。
ここでは、一般的な株式会社の設立を例に、具体的な流れを解説します。
ステップ1 会社の基本事項を決める
登記申請の前に、会社の憲法ともいえる「定款」に記載すべき基本事項を決定します。
これらは会社の根幹をなす重要な項目です。
- 商号(会社名):使用できる文字や記号にはルールがあります。同一本店所在地での同一商号は登記できません。念のため、法務局のオンラインシステムで類似商号がないか確認しておくと安心です。
- 本店所在地:会社の住所です。自宅やレンタルオフィス、バーチャルオフィスでも登記可能です。
- 事業目的:どのような事業を行うかを具体的に記載します。許認可が必要な事業は、その要件を満たす文言を入れる必要があります。将来行う可能性のある事業も記載しておきましょう。
- 資本金の額:会社法上は1円から設立可能ですが、資本金は会社の体力や信用度の指標となります。一般的には、初期費用と3~6ヶ月程度の運転資金を目安に設定すると良いでしょう。
- 発起人(出資者):会社を設立する人(お金を出す人)を決めます。
- 役員構成:会社の経営を行う取締役などを決めます。
- 事業年度(決算月):会社の会計期間を決めます。繁忙期を避け、消費税の免税期間を最大限活用できる月を選ぶのが一般的です。
ステップ2 定款を作成し認証を受ける
ステップ1で決めた基本事項をもとに、会社のルールブックである「定款」を作成します。
株式会社の場合、作成した定款を公証役場に持ち込み、公証人による「認証」を受ける必要があります。この認証により、定款が正当な手続きによって作成されたことが証明されます。
なお、電子定款を作成して電子認証を受ければ、通常必要な4万円の収入印紙が不要になるため、コストを抑えたい方におすすめです。(合同会社の場合は定款の作成は必要ですが、公証役場での認証は不要です。)
ステップ3 資本金を払い込む
定款の認証後、発起人(出資者)個人の銀行口座に、定められた資本金を振り込みます。
この時点ではまだ会社の銀行口座は作れないため、発起人代表の口座を使用します。
通帳の表紙、裏表紙、そして資本金の振込が記帳されたページをコピーしたものが「払込証明書」となり、登記申請の際に必要となります。
ステップ4 法務局へ登記申請を行う
必要書類がすべて揃ったら、本店所在地を管轄する法務局に登記申請を行います。
登記申請書、定款、資本金の払込証明書、役員の就任承諾書、印鑑証明書などを提出します。
書類に不備がなければ、申請から1週間~10日ほどで登記が完了します。
この法務局へ登記申請書を提出した日が、会社の設立日となります。
ステップ5 税務署などへ設立の届出を行う
登記が完了したら、会社設立は完了ですが、事業を開始するためには各種行政機関への届出が必要です。
特に税務署への届出は、その後の納税額に大きく影響するため非常に重要です。
- 税務署:法人設立届出書、青色申告の承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書など
- 都道府県税事務所:法人設立届出書
- 市町村役場:法人設立届出書
特に「青色申告の承認申請書」は、設立から3ヶ月以内という提出期限があり、これを逃すと初年度は節税メリットの大きい青色申告が利用できなくなるため、登記完了後すぐに手続きを行いましょう。
ステップ6 社会保険の手続きを行う
法人は、社長一人であっても社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が法律で義務付けられています。
管轄の年金事務所で手続きを行います。
また、従業員を一人でも雇用する場合は、労働保険(労災保険・雇用保険)の加入手続きも必要です。
こちらは労働基準監督署やハローワークが窓口となります。
専門家(税理士・司法書士)に相談するメリット
会社設立の手続きは自分自身で行うことも可能ですが、非常に複雑で専門的な知識が求められます。
時間や手間を考慮すると、専門家への依頼も有効な選択肢です。
会社設立における主な専門家は「司法書士」と「税理士」です。
- 司法書士:定款の作成・認証や登記申請といった、会社設立の法的な手続きを代行する専門家です。手続きを正確かつ迅速に進めてくれます。
- 税理士:法人設立届出書の作成や青色申告の承認申請など、税務に関する手続きや、設立後の顧問として経営をサポートする専門家です。節税を考慮した決算月の設定や役員報酬の額、創業融資の相談など、お金に関する幅広いアドバイスが期待できます。
専門家に依頼すると費用はかかりますが、本業に集中できる時間を確保でき、手続きのミスを防げるという大きなメリットがあります。
また、設立後の事業運営を見据えた専門的なアドバイスは、経営の安定に大きく貢献します。
特に税理士とは設立後も長い付き合いになることが多いため、目先の設立費用だけでなく、長期的な視点で信頼できるパートナーを探すことが成功の鍵となります。
まとめ
いきなり法人化は、税負担の軽減や社会的信用の向上など多くのメリットがある一方、設立コストや社会保険料といった負担が増えるデメリットも存在します。
そのため、ご自身の事業の売上予測や将来の展望を考慮し、個人事業主と比較して慎重に判断することが重要です。
本記事で解説したメリット・デメリットや判断基準を参考に、最適な選択をしてください。
後悔しないためには、判断に迷う場合は税理士などの専門家へ相談することをおすすめします。









