合同会社とは何か 基本的な特徴と株式会社との違い
合同会社(LLC:Limited Liability Company)は、2006年5月に施行された会社法により導入された比較的新しい会社形態です。
日常生活やビジネスにおいては「ローコストで設立でき、運営が柔軟」な法的枠組みとして注目されています。
日本国内の起業家や少人数で事業を行う法人で導入されるケースが増えています。
本章では、合同会社の基本的な特徴と、伝統的な会社形態である株式会社との違いについてわかりやすく解説します。
合同会社の主な特徴
- 出資した社員全員が原則として会社の業務執行に関与できる組織形態
- 社員の出資額に関わらず、利益配分や意思決定方法を柔軟に定款で定められる
- 設立費用や運営コストが比較的低い
- 社員全員が有限責任である
- 経営や利益配分に柔軟さがあるため、少人数・小規模の事業に向いている
「決算公告義務がない」「定款自治が高い」といった合同会社特有のメリットもあります。
株式会社との違い
株式会社と合同会社は、いずれも法人格を持ち、構成員の有限責任性を備えているという点では共通していますが、経営にかかわる仕組みや法律上の位置づけなどに以下のような違いがあります。
| 項目 | 合同会社(LLC) | 株式会社 |
|---|---|---|
| 設立費用 | 約6万円(登録免許税+定款認証不要) | 約20万円(登録免許税+定款認証必要) |
| 決算公告義務 | なし | あり(官報等への公告が義務) |
| 意思決定 | 社員の過半数など、定款で柔軟に決定可 | 株主総会・取締役会等の法定機関で決定 |
| 利益配分 | 出資比率に関係なく定款により自由 | 原則として出資比率(持株割合)による |
| 役員構成と任期 | 業務執行社員・代表社員(任期なし) | 取締役・代表取締役(最長10年で更新) |
| 知名度 | 株式会社に比べやや低い | 高い(信用力にも影響) |
| 公開性 | 株式公開不可 | 株式上場可能 |
合同会社の活用が向いているケース
「少人数で投資やベンチャービジネスを始めたい場合や、設立・維持コストを抑えたい場合は合同会社が適している」と言えます。
例えば、 土木建設業、コンサルティング業、不動産賃貸、ITスタートアップ、家族経営や士業法人などで合同会社が多く採用されています。
一方で、 「将来的に上場を目指す」「大規模な資金調達を行いたい」「ブランドイメージを重視する」といった場合は株式会社が選ばれています。
業務執行社員の概要 合同会社における位置づけ

合同会社における「業務執行社員」とは、会社の業務全般を実際に執行する権限および責任を持つ社員(出資者)のことを指します。
この役職は、会社法で定められる合同会社特有のものであり、株式会社における取締役や代表取締役に近い役割を果たしますが、出資と業務執行の権利・義務を兼ね備えているという点に大きな特徴があります。
合同会社では、出資者自らが業務執行社員として会社の経営に直接関与する形態が一般的です。
そのため、外部から経営者を招く株式会社とは異なり、出資者である社員自身が合同会社の意思決定や日々の業務執行を担うこととなります。
合同会社における業務執行社員の基本的な役割
業務執行社員は、合同会社の内部で以下のような重要な役割・責務を持っています。
| 役割・責務 | 具体例 | 該当法令 |
|---|---|---|
| 会社の業務執行 | 会社の日常業務、取引先との契約締結、対外的活動の推進 | 会社法第590条など |
| 意思決定 | 事業計画策定、重要事項の決議、社員間の調整 | 会社法第591条など |
| 法的代表 | 登記簿上の代表署名、官公庁への届出・申請 | 会社法第599条など |
株式会社との比較における位置づけ
株式会社では株主と取締役、代表取締役と役割が明確に分かれていますが、合同会社では社員が直接業務執行権を持つ点が大きく異なります。
| 会社形態 | 所有と経営の分離 | 業務執行者 | 特徴 |
|---|---|---|---|
| 合同会社 | 不可(基本的に社員が兼務) | 業務執行社員(=出資社員) | 社員自らが経営し、意思決定・執行を行う |
| 株式会社 | 可(経営陣は株主でなくても可) | 取締役・代表取締役 | 株主は間接的に経営に携わる |
業務執行社員が持つ権限と制限
業務執行社員は、合同会社の業務全般に対する執行権限を持ち、社員全員の同意や定款の定めによってその範囲や役割分担が柔軟に設計できます。
ただし、会社法や定款により、その裁量には一定の制限が設けられる場合もあるため、事前に権限分担や意思決定のルールを明確にしておく必要があります。
このように、合同会社では業務執行社員が組織運営の中核となる存在であり、その役割と責任の範囲を正しく理解することが、安定した会社経営につながります。
業務執行社員の主な役割

合同会社における業務執行社員は、株式会社における取締役に相当する経営実務の中心的存在として、会社運営の意思決定から対外的な手続き、日々の事業管理に至るまで多岐にわたる役割を担います。
以下では、その主な役割について具体的に解説します。
組織運営と意思決定
業務執行社員は、合同会社のビジネス戦略や経営方針など、会社の重要事項を決定し、実際に事業運営を担う存在です。
通常、業務執行社員が複数いる場合は、社員間の合議によって経営方針が定められます。
日常業務の執行から、資本政策・組織変更・出資者とのやりとりなど、組織全体の運営に関わる重要な判断を行います。
| 意思決定事項 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 経営戦略の策定 | 新規事業の開始、サービスラインの拡充、資金調達方法の決定など |
| 予算編成・事業計画 | 年間予算の決定や各部門における事業目標の設定 |
| 組織体制の見直し | 人事異動、部門新設・廃止、役割分担の調整 |
外部との契約や法的手続き
業務執行社員は、会社を代表して取引先・顧客・金融機関など外部との契約締結、官公庁への届出や法務局での登記手続きなどの法的手続きを遂行します。
会社印の押印や契約書署名など、会社を法的に代表する立場での実務を担うことが特徴です。
また、税務申告や社会保険関連の届出など会社遵法義務に関わる重要な役割も担います。
| 対外交渉・手続き項目 | 主な業務内容 |
|---|---|
| 契約締結 | 売買契約、業務委託契約、賃貸借契約などの締結と管理 |
| 登記手続き | 会社設立・変更・解散に関する登記の申請 |
| 行政届出 | 各種許認可の申請や変更、税務署・労働基準監督署等への届出 |
経営責任と義務
業務執行社員には、会社の経営に関する包括的な責任と義務が課せられます。具体的には、忠実義務や善管注意義務に従い、会社および他の社員に損害を与えないよう誠実に業務を遂行する必要があります。
また、会社財産の管理にあたり、帳簿の記録・情報開示、出資者への説明責任なども求められます。
事業運営に関する法令遵守や内部規律の整備も重要な役割の一つです。
| 責任・義務の内容 | 具体例 |
|---|---|
| 忠実義務 | 自己の利益よりも会社の利益を優先して判断する |
| 善管注意義務 | 一般的な経営者として必要な注意と配慮をもって事業を進める |
| 情報開示責任 | 社員や出資者に対して適時適切な情報提供を行う |
| 法令遵守 | 会社法や税法等の関係法令を守る |
業務執行社員の責任範囲

法的責任
合同会社の業務執行社員は、会社の業務全般を担う立場であり、法令や定款に反する行為をした場合には、会社および第三者に対して損害賠償責任を負う可能性があります。
これは、例えば取締役がいる株式会社の場合と同様で、公正かつ誠実な業務執行が求められます。
特に法人の代表として対外的に行動する際には、商法や会社法、税法、労働法など関連する法規を順守しなければなりません。
また、重大な義務違反や背任行為があった場合は、損害賠償請求を受けるリスクもあるため注意が必要です。
債務の責任と有限責任
合同会社の社員は、その出資額を限度として会社の債務について責任を負います。
すなわち業務執行社員であっても、株式会社の株主と同じく「有限責任社員」という立場にあります。
会社が万が一債務超過となった場合でも、社員個人の財産が自動的に差し押さえられることはありません。
ただし、会社の名義で不正な取引を行った際や、個人保証をしている場合などは、例外として個人にまで債務の負担が及ぶことがあります。
| 責任の種類 | 内容 | 注意点 |
|---|---|---|
| 法的責任 | 会社法・民法など関係法令遵守。損害賠償責任あり。 | 規定違反行為に厳しい制裁。背任・横領などは刑事責任に発展することも。 |
| 債務に対する責任 | 出資額を上限とする有限責任。 | 個人保証や違法行為の場合、無限責任に近い負担となることがある。 |
業務執行社員と出資社員の責任の違い
合同会社では、全ての社員(ここでの社員とは出資者を指す)が法的には有限責任を負いますが、業務執行社員には業務全般の運営責任が課されます。
一方、業務に関与しない出資社員(非業務執行社員)は、会社運営の意思決定や実務執行には直接関与しません。
そのため、日常的な業務や経営判断においては、業務執行社員がより強い責任を負う立場となります。
| 社員の種類 | 業務執行権限 | 責任 |
|---|---|---|
| 業務執行社員 | 有(会社代表、業務遂行が主な役割) | 法的責任+有限責任(出資額まで) |
| 出資社員(非業務執行) | 原則無(経営への直接関与なし) | 有限責任(出資額まで) |
このように、合同会社における業務執行社員は、有限責任の範囲内で会社運営上の日常的な決定や対外的業務を担う分、通常の出資社員よりも実務的な責任が重くなる点に留意が必要です。
業務執行社員の設置方法
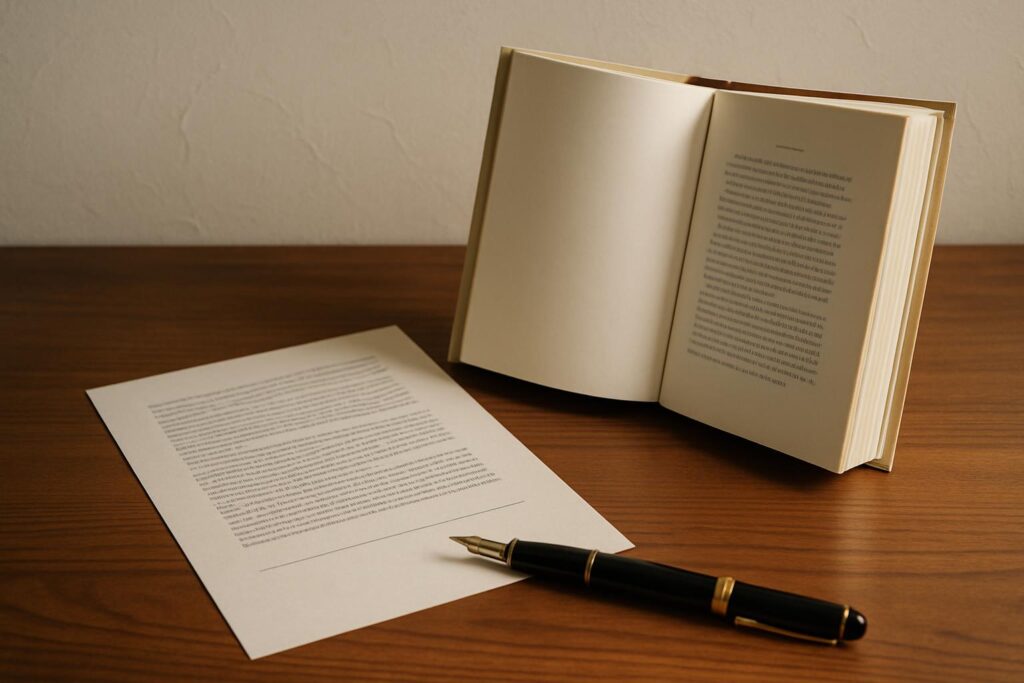
定款による定め
合同会社における業務執行社員の設置は、定款により具体的に定める必要があります。
合同会社では全社員が業務執行権限を持つのが原則ですが、定款において社員の中から業務を執行する者を限定することができます。
たとえば、複数名の社員のうち数名だけを業務執行社員とし、他の社員は出資のみ行う体制も可能です。
このように、合同会社の柔軟な組織運営を可能にするポイントが定款による業務執行社員の定めです。
| パターン | 定款での記載例 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 全社員が業務執行 | 特に限定せず「社員が業務を執行する」旨を記載 | 意思決定が迅速だが少人数向け |
| 一部社員のみ業務執行 | 「AとBを業務執行社員とする」等、氏名で特定 | 出資のみの社員と執行社員を分けられる |
| 将来の変更を予定 | 業務執行社員の変更方法も定めておく | 組織の成長や変化に柔軟に対応可能 |
設置の手続きと登記
業務執行社員を正式に設置するためには、定款の作成だけでなく、法務局への登記手続きが必須です。
設立登記の際には、社員の氏名または名称・住所のほか、業務執行社員となる者を記載し、公証人の認証は不要ですが、合同会社の設立登記申請書に必要事項を記載して提出します。
また、業務執行社員が法人である場合は、その代表者の情報も合わせて登記する必要があります。
これにより社外への責任主体が明確となり、取引先や金融機関も安心して取引ができる仕組みとなっています。
| 業務執行社員設置に必要な主な書類 | 概要 |
|---|---|
| 定款 | 業務執行社員の記載含む |
| 設立登記申請書 | 業務執行社員の詳細を記載 |
| 代表社員の就任承諾書(代表社員がいる場合) | 代表社員の就任を証明 |
| 本人確認書類 | 自然人であれば住民票、法人なら法人登記簿謄本等 |
業務執行社員の変更・追加・退任方法
業務執行社員を途中で追加・変更・退任する場合には、原則として定款の定めに従った社員総会などの手続きを経る必要があります。
変更後は、速やかに変更登記を行うことが法務局への義務となっています。
社員が新たに就任または退任した場合、変更登記の申請期限は2週間以内です。
遅れると過料が科される可能性があります。
また、定款が業務執行社員の選任や解任について特別な手続きを定めている場合、そのルールに従う必要があります。
| 主なケース | 必要な手続き | 注意点 |
|---|---|---|
| 追加 | 社員総会決議、定款の変更、登記申請 | 新社員の同意書・本人確認書類が必要 |
| 変更 | 定款変更(または社員総会決議)、登記申請 | 定款手続きの要否を確認 |
| 退任 | 退任届出、総会決議(必要な場合)、登記申請 | 登記申請期限を遵守 |
業務執行社員の設置および変更に関わる手続きは、定款・会社法・登記に十分注意を払い、正確かつ速やかに進めることが重要です。
役員構成の変更は社外への印象や会社運営にも直結するため、法定手続や書式に漏れがないよう確認しましょう。
業務執行社員にふさわしい人材とは

合同会社の業務執行社員は、会社運営の中核を担う重要な役割です。
そのため、業務執行社員としてふさわしい人材には、実務能力だけでなく判断力やリーダーシップ、誠実性など多角的な資質が求められます。
また、組織内外のステークホルダーと円滑な関係を築く対人スキルも不可欠です。
以下に、業務執行社員に必要なスキルや資質、そしてその背景にある理由について詳しく解説します。
求められるスキルや資質
業務執行社員は、合同会社の経営・運営だけでなく、対外的な法的手続きや契約締結なども担うため、多岐にわたる能力が求められます。
その主なものを整理します。
| スキル・資質 | 具体的内容 | 重要な理由 |
|---|---|---|
| リーダーシップ | 意思決定を主導し、組織を統率する力 | 経営方針の策定やメンバーの意見調整に必要 |
| 経営知識 | 財務・会計・法務・労務などの知識 | 業務運営とコンプライアンス確保に不可欠 |
| コミュニケーション能力 | 社員や取引先との信頼構築・交渉力 | トラブル防止やスムーズな業務進行のため |
| 誠実性・倫理観 | 信頼される対応、法令順守の姿勢 | 社会的信用の維持と債務・法的責任回避に直結 |
| 柔軟性と対応力 | 変化に素早く適応し、適切に判断・対応 | 市場や法令の変化がある中で持続的成長を図るため |
これらの資質を備えた人材が業務執行社員となることで、会社経営の安定や健全な成長が期待できます。
よくあるトラブル事例と防止策
業務執行社員の選任をめぐっては、トラブルが発生しやすいポイントがあります。
注意すべき具体的事例と、それに対する予防策を整理します。
| トラブル事例 | 背景・要因 | 防止策 |
|---|---|---|
| 意思疎通の不足による内部対立 | 事業方針や役割分担が不明確 | 定期的なミーティングと業務分担の明確化 |
| 法令違反による行政指導・訴訟 | 法務知識やコンプライアンス意識の不足 | 法務・会計などの外部専門家の活用 |
| 業績不振や資金繰り悪化 | 事業計画の甘さ・リスクマネジメントの不足 | 定期的な経営分析と相談体制の構築 |
| 業務執行社員の独断専行 | 情報の独占や報告義務の怠慢 | 決算報告書や議事録の作成・公開 |
以上のような事例を踏まえ、業務執行社員には誠実な姿勢で組織運営することや、外部専門家との連携、定期的な情報共有体制の整備が大切です。
透明性とコミュニケーションを重視することで、スムーズで健全な合同会社の運営が実現できます。
合同会社の業務執行社員についてよくある質問

兼任や報酬の有無
合同会社における業務執行社員は、原則として他の社員と兼任が可能です。
例えば、出資社員がそのまま業務執行社員を務めることもできますし、代表社員と業務執行社員を兼ねることもできます。
また、個人だけでなく法人も業務執行社員になることが可能です。
報酬については、会社の定款や社員間契約で自由に定められます。
業務執行社員が役務の対価として報酬を受け取るかどうかは、必ずしも法律で定めがあるわけでなく、社員全員の合意によって決まります。
報酬を支払う場合は、税務上「役員報酬」もしくは「業務委託費」として処理が必要となる点にも注意しましょう。
| ケース | 兼任可否 | 報酬の有無 |
|---|---|---|
| 出資社員兼業務執行社員 | 可能 | 合意により決定 |
| 外部人材のみ業務執行 | 可能 | 合意により決定 |
| 法人が業務執行社員 | 可能 | 合意により決定 |
代表社員との違い
代表社員は、社外に対して会社を代表する役割を担います。
一方、業務執行社員は会社の「業務の執行」すなわち経営上の意思決定を担当します。
合同会社では、原則として業務執行社員の中から代表社員を選任しますが、業務執行社員全員が代表社員となることも、一部の社員のみを代表社員とすることも定款で定められます。
| 役割 | 主な機能 | 選任方法 |
|---|---|---|
| 業務執行社員 | 会社経営および業務の執行 | 定款または社員の合意による |
| 代表社員 | 会社の代表権行使(対外的な契約締結等) | 業務執行社員の中から選任 |
人数や選任基準
合同会社の業務執行社員は1名から設置できます。
社員が複数いる場合は、全員が業務執行社員となることも、一部のみとすることも可能です。
人数には上限はありません。
業務執行社員の選任基準に関して法律上の制約はなく、社員の合意または定款の定めに基づいて決定されます。
未成年者や法人も業務執行社員になることができますが、登記の際には登記事項証明書や印鑑証明書等所定の書類が必要となる場合があります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 人数 | 1名以上(上限なし) |
| 選任の基準 | 社員間の合意・定款記載 |
| 法人・未成年者 | いずれも可能だが、必要書類に留意 |
まとめ
合同会社の業務執行社員は会社運営の中核を担い、その選任や役割、法的責任には株式会社と異なる独自の特徴があります。
定款の定めや手続きに基づき業務執行社員を設置・変更することで、円滑な経営と法的リスク管理が可能となります。
適切な人材選びと明確な責任分担が、合同会社の健全な運営に不可欠です。









