株式会社を1人で設立できる理由
1人株式会社とは何か
1人株式会社とは、株主や取締役が一人だけで設立・運営できる株式会社のことを指します。
従来の日本の会社法では、株式会社を設立するためには複数人の発起人や取締役が必要とされていました。
しかし、現在では1人だけでも株式会社の設立が可能となっており、個人事業主やフリーランスの方でも法人格を持って活動することができるようになっています。
1人株式会社の場合、発起人・株主・取締役をすべて同一人物が兼ねても問題ありません。
そのため、設立後の経営方針や意思決定も柔軟かつ迅速に行うことができます。
個人が全ての持ち株を保有することで、経営権や所有権が完全に一致し、他者の影響を受けずにビジネス展開できる点が大きな特徴です。
会社法で認められている背景
2006年の会社法施行により、株式会社設立の要件が大幅に緩和され、1人でも株式会社を設立できるようになりました。
この改正により、起業のハードルが下がり、個人や小規模事業者による法人設立が急増しました。
| 旧商法 | 現行会社法 |
|---|---|
| 発起人2名以上が必要 | 発起人1名でも可 |
| 取締役3名以上が原則 | 取締役1名でも可 |
| 監査役設置が原則 | 監査役は任意 |
このような背景としては、個人事業主やベンチャー起業家がより簡単に株式会社という法人格を活用して事業展開できるようにするために、会社設立の規制緩和が行われた点が挙げられます。
また、会社法改正により有限責任制度が徹底され、会社の負債について出資額以上の責任を負わない仕組みが明確になりました。
これにより1人で会社を設立しても、個人の資産とは分離してリスクを管理できるため、安心して法人化できる土壌が整いました。
このような法的背景から、現在では多くの起業家やフリーランスが、自分一人だけで株式会社を設立し、ビジネスの信用力向上や節税のメリットを享受しています。
1人で株式会社を設立する際のメリットとデメリット

1人株式会社のメリット
信用力の向上
1人で株式会社を設立する最大のメリットの一つは、社会的な信用力が向上する点です。
個人事業主と比較すると「株式会社」として事業を行うことで、銀行からの融資や取引先との契約、採用活動など、あらゆるビジネスシーンで信頼度が増します。
特に資金調達や大手企業との取引では、法人格があるか否かが重要なポイントになります。
節税効果
株式会社にすることで各種税制上の優遇措置や経費計上の幅が広がり、結果として節税メリットを享受できます。
役員報酬として所得を分散させることで所得税負担の軽減が図れる他、経費として計上できる範囲が個人事業主よりも広くなります。
また、決算期の選択や繰越欠損金の利用等、法人ならではの税務戦略も有効です。
有限責任の活用
株式会社の株主は、出資額を限度とした有限責任しか負いません。
つまり、会社の事業が不調に終わり多額の負債が発生しても、自身の個人財産まで責任を負う必要は原則としてありません。
この有限責任制度により、リスクをコントロールしつつ事業活動に専念できます。
1人株式会社のデメリット
運営コスト
株式会社の設立および維持には個人事業に比べて高額なコストがかかります。
設立費用として定款認証代や登録免許税、運営開始後は事務所家賃や登記の維持費なども必要です。
さらに、赤字であっても発生する「法人住民税均等割」など、経済的な負担が一定程度発生します。
社会保険加入義務
1人株式会社であっても、社会保険(健康保険・厚生年金)への加入が義務付けられます。 これにより、個人事業主の場合と比べ社会保険料の負担が大きくなることがあります。保険料の納付を怠ると、追加徴収や行政指導等のリスクも生じます。
手続き・管理の負担
会社経営は法的な手続きや書類作成、帳簿管理といった事務が煩雑になります。
決算書の作成や税務申告、総会議事録の作成など、法律で求められる手続きが多く、事業に専念できる時間が削がれる可能性もあります。
また、すべてを1人でこなす場合はオーバーワークやミスのリスクも高まります。
| 項目 | メリット | デメリット |
|---|---|---|
| 信用力 | 法人格により対外的な信用力が大きく向上 | - |
| 税制 | 節税戦略や経費計上の幅が広がる | 赤字でも法人住民税などの固定費が発生 |
| 責任 | 有限責任でリスクを限定できる | - |
| 社会保険 | 厚生年金等の社会保障が充実する | 社会保険加入義務があり負担が増加 |
| 手続き | - | 会計・税務・法的手続きが煩雑 |
| 運営コスト | - | 設立・運営ともにコストが高い |
株式会社を1人で設立する際の必要条件
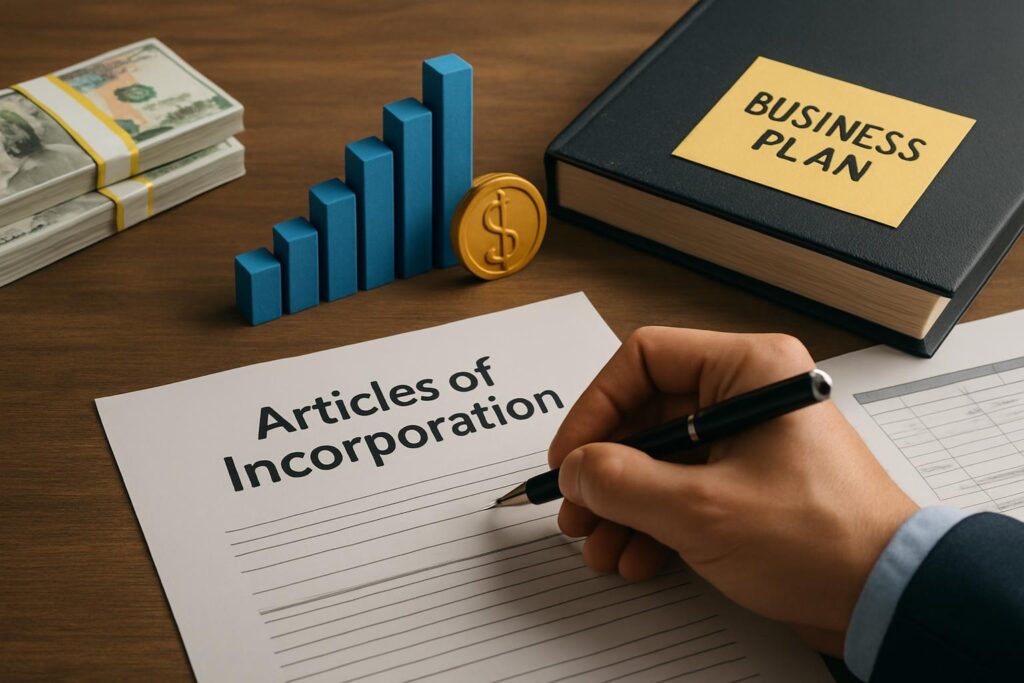
株式会社を1人で設立するためには、会社法で定められた複数の条件や必要書類を満たす必要があります。
ここでは、具体的にどのような準備や手続きが必要かを解説します。
十分な事前準備を行うことでスムーズな設立手続きが可能となります。
資本金の準備
株式会社設立に際しては、会社の運営資金として資本金を用意する必要があります。
日本の会社法では資本金1円からでも設立が可能ですが、資金が少なすぎると信用力の面で不安が残ります。
実務的には、数十万円~数百万円程度を目安に準備するケースが多いです。
資本金は、設立時に代表者の個人口座へ払い込みを行い、その証明を後述する書類で用意します。
定款の作成と認証
株式会社を設立するには、「定款」の作成と公証人による認証が不可欠です。
定款は会社の基本的なルールや事業目的などを明記した書面で、設立時には公証人役場での定款認証手続きが必要となります。
定款の作成にあたり、会社の名称・本店所在地・事業目的・発起人の氏名と住所・発行可能株式総数・設立に際して出資される財産の価額など法定事項を正確に記載する必要があります。
電子定款の場合は印紙代の節約も可能です。
役員や株主の要件
1人株式会社の場合、発起人・株主・取締役はすべて一人で兼任することができます。
ただし、公序良俗に反しない人物であり、成年被後見人や被保佐人でないことが条件です。
また、代表取締役については1名で問題ありませんが、設立時の役員任期や、登記事項の記載漏れなどには注意することが必要です。
| 役割 | 人数要件 | 主な注意点 |
|---|---|---|
| 発起人 | 1人で可 | 日本国籍でなくても可、出資義務あり |
| 取締役 | 1人で可 | 未成年の場合は親権者の同意等必要 |
| 株主 | 1人で可 | 法人でも個人でも可 |
| 代表取締役 | 1人で可 | 原則、取締役=代表取締役となる |
設立に必要な書類一覧
株式会社設立時には、法務局や公証人役場などへ提出するため、以下の書類を揃える必要があります。
漏れのないように準備しましょう。
| 書類名 | 概要 | 作成・取得方法 |
|---|---|---|
| 定款 | 会社の基本ルールを定めた書類。紙定款or電子定款。 | 自作または専門家委託+公証人認証 |
| 発起人の決定書 | 本店所在地や取締役選任など設立時事項を決議 | 発起人が自署 |
| 取締役等の就任承諾書 | 役員が役職に就任することの承諾書 | 当人が自署 |
| 印鑑証明書 | 発起人・取締役の印鑑証明 | 市区町村で発行 |
| 資本金の払込証明書 | 資本金を払込した証明 | 金融機関の取引明細書等を添付 |
| 登記申請書 | 会社設立の登記に必要な書類 | 法務局所定書式 |
| 印鑑届出書 | 会社の実印(代表者印)を届け出る書類 | 法務局所定書式 |
これらの書類は設立登記に必須です。
不備があると登記が受理されませんので、慎重に確認してください。
株式会社を1人で設立する具体的な手順

設立準備と事前のチェックポイント
株式会社を1人で設立する際には、まず事前準備として必要書類や資本金の用意、事業目的や会社名(商号)、本店所在地の決定など、多くのポイントを整理しておくことが重要です。
以下の点をチェックリストとして確認してください。
| チェックポイント | 内容 |
|---|---|
| 商号(会社名)の決定 | 同一住所で類似する商号がないか法務局で事前確認が必要 |
| 本店所在地の決定 | 自宅・レンタルオフィスも可能、賃貸物件の場合は管理規約の確認が必要 |
| 事業目的の設定 | 将来的に行いたい事業も含め、具体的で広めに記載するのが一般的 |
| 資本金額の決定 | 1円から可能だが、信用力を意識した適切な額を検討 |
| 発起人・取締役の決定 | 1人でも設立可能(1人が発起人と取締役を兼任可) |
定款の作成と公証人役場での認証
次に、会社のルールである定款を作成します。
定款には「商号」「目的」「本店所在地」「発行可能株式総数」「設立時発行株式数」「資本金額」「発起人や取締役の氏名住所」などの項目を記載します。
電子定款の場合は印紙代が不要になるため、コスト削減のためにもおすすめです。
作成した定款は、必ず公証人役場で認証を受ける必要があります。
役場への持参または電子定款でのオンライン申請が可能です。
認証手数料や謄本手数料がかかりますので、事前に費用も確認しましょう。
資本金の払込み手続き
定款が認証されたら、発起人個人名義の銀行口座に資本金を払い込みます。
払込証明のため、通帳の表紙や取引明細のコピーが必要となります。
会社名義の口座は設立後でないと作れないため、設立までは発起人の口座を利用します。
| 必要書類 | ポイント |
|---|---|
| 通帳表紙・明細のコピー | 資本金払い込み日や金額がはっきり分かる部分 |
| 払込証明書 | 発起人が作成し実印を押印 |
法務局での登記申請
資本金の払込みまで完了したら、会社設立の登記申請書類をすべて揃え、所轄の法務局に申請します。登記書類には定款(原本・コピー)、発起人や取締役の印鑑証明書、登記申請書、払込証明書などが含まれます。提出日=会社の設立日となるため、スケジュール管理も大切です。
併せて、会社の実印を作成し、登記申請時に印鑑届出書を提出します。
税務署や役所への届出
登記が完了した後は、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場などへ各種届出が必要となります。
会社設立届出書、青色申告承認申請書、給与支払い事務所等の開設届、源泉所得税に関する届出、社会保険・労働保険の手続など、期限が決まっているものが多いため、速やかに手続きを行いましょう。
| 提出先 | 主な内容 |
|---|---|
| 税務署 | 法人設立届出書、青色申告承認申請書、給与支払事務所等の開設届出書 |
| 都道府県税事務所・市区町村役場 | 法人設立届出書 |
| 年金事務所・労働基準監督署 | 社会保険新規適用届、労働保険(労災・雇用保険)手続 |
以上が、株式会社を1人で設立する際の全体の流れと具体的な手順です。事前準備やスケジュール管理をしっかり行うことで、スムーズに設立手続を進めることができます。
1人株式会社の設立にかかる費用と期間

登録免許税や定款認証費用
1人で株式会社を設立する場合、設立手続きに必要な費用は主に「定款認証費用」「登録免許税」「その他の実費」に分類されます。
それぞれの費用項目の概要と標準的な金額を下記の表にまとめました。
| 項目 | 金額(目安) | 備考 |
|---|---|---|
| 定款の認証手数料 | 約52,000円 | 公証人へ支払う手数料 |
| 定款の謄本手数料 | 約2,000円(1冊) | 追加で提出用が必要な場合あり |
| 定款の印紙税 | 40,000円 | 電子定款の場合は不要 |
| 登録免許税 | 150,000円(最低額) | 資本金の0.7%(ただし下限15万円) |
| 印鑑作成費用 | 約10,000円〜 | 実印・銀行印・角印のセットが一般的 |
| その他実費 | 数千円〜 | 郵送費・証明書取得費用など |
総額としては、株式会社の設立にはおよそ200,000円から250,000円程度が必要となるケースが一般的です。
ただし、電子定款を利用する場合、印紙代40,000円が不要となるため、大きな節約になります。
士業に依頼する場合は、さらに数万円~10数万円の報酬が加算されます。
設立までのスケジュール目安
1人株式会社の設立に必要な期間は、全体で約2週間〜1か月程度が一般的な目安です。
各工程での標準的な所要日数を下記に示します。
| 工程 | 標準的な日数 | ポイント |
|---|---|---|
| 定款作成・認証 | 3〜5日 | 事前準備や文案確認の時間も含める |
| 資本金の払込み | 1日 | 発起人名義の口座へ振込 |
| 設立登記の申請 | 1日 | 必要書類一式を法務局に提出 |
| 登記完了 | 約1週間程度 | 法務局による審査期間 |
| 会社設立日以降の諸届け | 1日〜数日 | 税務署・都道府県税事務所・年金事務所等 |
急ぎで手続きを進める場合は最短1週間程度で設立登記まで完了することも可能です。
ただし、書類の不備があった場合や、公証人役場・法務局が混み合っている場合には時間を要することもありますので、余裕をもったスケジュール管理をおすすめします。
また、会社の本店所在地を賃貸オフィスにする場合などは契約に時間がかかる場合があるため、設立までの期間に影響が出ることもあります。
事前に各準備事項をチェックし、円滑な設立手続きを進めましょう。
設立後の運営と注意点

1人の場合の取締役や株主総会のポイント
株式会社を1人で設立した場合、取締役と株主が同一人物となる点が大きな特徴です。
この場合でも会社法上、取締役会は設置不要であり、ひとり取締役でも問題ありません。
株主総会も、法律上きちんと開催したことを記録する必要があり、自分一人で意思決定した内容について議事録の作成が求められます。
実態として「1人会議」であっても、各決議事項について議案、決議内容、決議日などを正確に記録することが重要です。
これらの記録は、税務調査や法的トラブル、資本金増資や事業承継時など、様々な場面で必要となるため確実に保存しましょう。
| 必要な議事録 | 内容例 | 記録のタイミング |
|---|---|---|
| 定時株主総会議事録 | 決算承認、役員報酬決定など | 年1回の決算後 |
| 臨時株主総会議事録 | 商号や本店所在地変更、目的変更など | 必要に応じて随時 |
| 取締役決定書 | 会社の実務運営(契約締結、事業拡大など) | 発生ごと |
会計・税務の管理方法
株式会社設立後は、日々の会計記帳や決算作業、法人税・消費税などの納税業務を適切に行う必要があります。
特に1人で経理・税務を管理する場合、専門知識が求められ負担が大きくなることが多いです。
また、法人は個人事業主よりも税務調査を受けるリスクも高まるため、帳簿の適正な作成や証憑類の保存体制が重要となります。
税理士や会計ソフトの活用
税務や会計業務が煩雑な場合は、弥生会計やfreee、マネーフォワードなどの会計ソフト導入を検討しましょう。
特にインボイス制度(適格請求書発行事業者登録制度)が始まったことで、経費や仕入に関する情報も厳格に管理する必要が出てきています。
不明点や節税対策については、顧問税理士に相談するのが効果的です。
月額数千円から外部の税理士に業務を依頼するケースも多く、社会保険や給与計算などのサポートまで任せることも可能です。
| 管理方法 | 主な特徴 | おすすめ対象者 |
|---|---|---|
| 自分で管理(会計ソフト利用) | コストを抑えやすい。入力・帳簿作成の手間あり。 | 経理経験がある、コスト重視の起業家 |
| 税理士に依頼 | 専門家のアドバイスで安心。費用がかかる。 | 本業に集中したい方、節税重視の方 |
社会保険と労働保険の手続き
株式会社として事業をスタートした場合、たとえ代表取締役1名だけであっても、役員報酬を設定することで社会保険(健康保険・厚生年金保険)への加入が法律上義務化されます。
これは個人事業主との大きな違いです。新規適用の手続きは、日本年金機構や全国健康保険協会を通じて行い、設立から5日以内の提出が推奨されています。
また、労働保険(労災保険・雇用保険)は1人会社の場合は原則として不要ですが、アルバイトや従業員を新たに雇用する場合は追加で加入手続きが発生します。
社会保険の保険料は会社と個人(役員)が折半するため、資金計画やキャッシュフロー管理にも十分注意しましょう。
| 手続き名 | 必要なタイミング | 提出先 |
|---|---|---|
| 社会保険新規適用届 | 設立後速やかに(5日以内目安) | 日本年金機構・全国健康保険協会 |
| 労働保険保険関係成立届 | 従業員雇用時 | 労働基準監督署・ハローワーク |
1人株式会社に向いている人・業種

1人で株式会社を設立・運営することには、適性や事業内容が大きく関わります。
ここでは「どのような人や業種が1人株式会社に向いているのか」について解説します。自身とビジネスが該当するかどうか、参考にしてください。
フリーランスや個人事業主との比較
個人事業主やフリーランスと株式会社設立のどちらが自分に適しているかを比較検討することは重要です。
特に以下のような点で違いがあります。
| 比較項目 | 1人株式会社 | 個人事業主 |
|---|---|---|
| 信用力 | 高い(法人格により取引先・金融機関から信頼されやすい) | やや低い(事業規模や実績に依存) |
| 節税効果 | 対策が豊富(役員報酬や経費計上、退職金制度等) | 限定的(青色申告で一部優遇) |
| 責任範囲 | 有限責任(出資額まで) | 無限責任(個人資産まで責任) |
| 社会保険 | 原則加入義務有り | 任意加入 |
| 決算・税務手続き | 複雑(決算・申告要、税理士活用が一般的) | 比較的簡便(自力での申告も可能) |
法人としての信用や節税を重視したい場合は、1人株式会社が適しています。
一方でシンプルな事業運営やコストを抑えたい場合は個人事業主のままでも十分なケースもあります。
1人会社に適したビジネスモデル例
1人で株式会社を設立するのに適した業種やビジネスモデルにはいくつかの特徴があります。
下表に主な例をまとめます。
| 業種・ビジネスモデル | 1人株式会社が向いている理由 |
|---|---|
| IT・ウェブ制作、システム開発 | 業務委託によるBtoB取引が多く、法人格による信用力が評価されやすい |
| コンサルティング業(経営・税務・法務ほか) | 高単価取引や大手との契約時に法人格が信用材料になる |
| デザイナー・クリエイター業 | 著作権管理や請負契約などで法人化の利点が大きい |
| ネットショップ運営 | 取引先や仕入先との契約、決済機能などで法人が有利 |
| 不動産賃貸・不動産管理業 | 税務メリット、有限責任によるリスク限定などの点が有効 |
| YouTuber・インフルエンサー | 広告収入の管理及び節税目的、ビジネスの拡大が想定される |
| 士業(行政書士・社会保険労務士・弁理士等) | 許認可の要件を満たす、事務所開設や信頼性向上のため |
1人株式会社は、BtoB取引の多い分野や、契約時の信用力・リスクの分離・節税意義が強い業種に特に向いています。
反対に、小規模な飲食業や現場作業主体の職種、規模拡大の見込みが低い場合は必ずしも最適とは限りません。
また、将来的な人員拡張や法人化によるビジネススケールの拡大を目指す場合には、早い段階から1人株式会社としてスタートすることもメリットが大きいでしょう。
まとめ
株式会社は1人でも設立・運営が可能です。信用力の向上や有限責任、節税効果といったメリットがある一方で、運営コストや社会保険加入義務などのデメリットもあります。
設立には定款認証や法務局での登記が必要で、資本金や設立費用、各種手続きに注意が必要です。
自分の事業に合った形式か慎重に検討しましょう。









